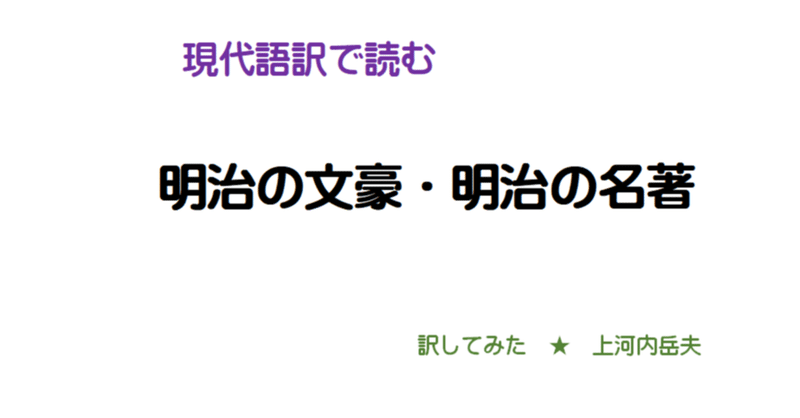
北村透谷「人生に相渉るとは何の謂ぞ」現代語訳

「人生に相渉るとは何の謂ぞ」は、北村透谷の評論の中で最も有名なものの一つである。この評論は山路愛山による頼山陽論(『頼襄を論ず』)に対する批判として書かれた。山路愛山の主張を知っておくことが、透谷の評論を理解する上で大きな助けになるので、愛山の頼山陽論の冒頭を引用する。
文章即ち事業なり。文士筆を揮ふ猶英雄剣を揮ふが如し。共に空を撃つが為めに非ず為す所あるが為也。万の弾丸、千の剣芒、若し世を益せずんば空の空なるのみ。華麗の辞、美妙の文、幾百巻を遺して天地間に止るも、人生に相渉らずんば是も亦空の空なるのみ。文章は事業なるが故に崇むべし、吾人が頼襄を論ずる即ち渠の事業を論ずる也。
現代語訳: 文章は、すなわち事業である。文士が筆を振るうのは、ちょうど英雄が剣を振るうようなものだ。どちらも空を撃つためではなく、なすべきことがあるためである。万の弾丸も千の剣鋒も、もし世の役に立たなければ、空の空である。華麗の辞、美妙の文が、幾百巻を残して天地の間にとどまっても、人生に関連しなければこれもまた空の空である。文章は事業であるがゆえに崇めるべきである。私が頼襄を論じるのは、すなわち彼の事業を論じるのである。
この格調の高い冒頭に引き続き、「頼春水大坂江戸港に在りて教授を業とす」という父親の記述に始まり、頼山陽の誕生から死までが記述され、『日本外史』などの仕事が事業として評価されている。透谷は、愛山の冒頭の見解を批判して、「人生に相渉るとは何の謂ぞ」すなわち「人生に関連するとはどういう意味か」と問いかけたのである。
この評論が書かれた当時、山路愛山と北村透谷は住居が近く頻繁に行き来する親しい関係であった。二人はキリスト教徒であり、江戸の伝統を継承する幸田露伴や泉鏡花の文学を批判するなど、意見が共通する所が多かった。ただ、二人が目指していた仕事の分野は大きく異なっていた。透谷の目が向けられていたのは詩や小説などの文芸の世界、一方愛山の目は評伝を初めとする歴史の世界に向けられていた。二人の文学観が対立するのは必然だっただろう。この論文に対する愛山の反論を契機として、いわゆる「人生相渉論争」が展開されることになる。
この評論は、詩人北村透谷の面目躍如、きわめて修辞性の高い記述が特徴である。論理的な視点からは読み解きにくい詩的表現や比喩的な表現が多用されていて、透谷の意図をどこまで把握できているのか、不安な所もある。現代語訳の底本としては、『キリスト者評論集』(新日本古典文学大系 明治編 26)、岩波書店、2002年12月刊行に所収のものを用いた。出原隆俊先生による校注から極めて多くのことを教えられた。先生の校注を訳文に利用させていただいたところもあることを明らかにして、深く感謝したい。
なお、以下の現代語訳において[ ]でくくられた部分は、訳者による記述である。
現代語訳 「人生に相渉るとは何の謂ぞ」
ー 文学が人生に関連するとは、どういう意味か ー
北村透谷 著、上河内岳夫 現代語訳
繊細で巧妙な文学は、思いがけず世間の嫌悪を招いて、異常なほど反対の動きが勢力を現わしてきた。愛山君が徳川時代の文豪の余風を襲って、「史論」と名づける鉄槌を振るうことになったのも、その現象の一つと見ることができる。徳富蘇峰の民友社に愛山君を起用させたのも、世間に愛山君を歓迎させたのも、この反対運動の勢力が鬱勃としたあまりであろう。
反対の動きは愛山君を載せて走った。そうして今や愛山君は反対の動きを載せて走ろうとする。彼は「史論」と名づける鉄槌で撃破すべき目的を拡大して、しきりに純文学の領地を襲おうとする。反対の動きにその勢いをほしいままにさせることは私も異存はない。ただ反対の動きを載せて、他の反対の動きを起こさせるほど遠くまで走ろうとするのを見る時に、反対の動きから反対の動きへと漂うという運命を、我が文学に与えることを悲しまずにはおれない。愛山君は、文章がすなわち事業であることを認めて、頼山陽論『頼襄を論ず』の冒頭で宣言した。何ゆえに事業なのか。愛山君は、これを解いて、「第一に、なす所があるためである。第二に、世間の役に立つがゆえである。第三に、人生に関連するがゆえである」と言っている。
そうして彼はまた文章が事業ではありえない条件を挙げて、「第一に、空を撃つ剣のようなもの。第二に、空の空なるもの。第三に、華辞妙文[華麗な辞、美妙な文]で人生に関連しないもの」と言っている。そうして彼はこの冒頭を「文章は事業であるがゆえに崇めるべし、私が頼山陽を論じるのは、すなわち彼の事業を論じるのである」と結んでいる。
立派な男が世に出ると、必ず一つ抱負があるに違いない。されどその抱負が、必ずしも見るべき功績に結びつくわけではない。建築家が苦心してその仕事に従うと、幾多の歳月を費やした後、確実に高く大きな楼閣を建てるという目算がある。されど人間の霊魂を建築しようとする技師になると、その費やす労力が直ちに有形の楼閣となって、ニコライ堂のように衆目を引くことができるものではない。衆目衆耳を驚かすことのない事業であって、あるいは大いに世界を震撼させることがあるのである。
天下に極めて無言な者がある、山岳である。されど彼は絶大な雄弁家である。もし言の有無で弁の有無を争うと、すべての自然は極めて憐れむべき沈黙の徒であろう。されど常に無言で常に雄弁であるのは、自然に加えるものはない。人間で自然のように無言である者があれば、愛山君一派の論士はその傍らに来て、「お前はどうして話さないのか」とあざけるだろうか。
人間のなす所もまた同様である。極めて拙劣な生涯の中に、最も高尚な事業を含むことがある。極めて高尚な事業の中に、最も拙劣な生涯を抱くことがある。外部から見られることでは、見ることができない内部を語りがたい。盲目である世眼を盲目のままで睨ませて、真摯な霊剣を空の彼方に撃つ雄士は、人間が感謝を払わずに恩沢を蒙る神のようなものである。天下には、なす所なく終わり、事業らしい事業を残すこともなく去り、そうして自ら十分に満足し自らよく信じて、死者の世界に移る英雄がある。私が最もよく同情を表さざるを得ない所である。
私は、人間は戦うために生れたことを記憶している。戦うのは、戦うために戦うのではなくて、戦うべきものがあるがゆえに戦うことを記憶している。戦うには、剣でするのがあり、筆でするのがある。戦う時は必ず敵を認めて戦うのであり、筆でするのと剣でするのと、戦うことに相異なるところはない。されど敵とするものの種類によって、戦う者の戦いを異にするのは当然である。戦う者の戦いの異なることによって、勝利の趣も異ならざるをえない。戦士は合戦に臨んで敵に勝ち、凱歌を唱えて家に帰る時、友人は祝して勝利と言い、批評家は評して事業という。事業は尊ぶべきであり、勝利は尊ぶべきである。そうではあるが優れた戦士は、このように勝利を携えて帰らないことがある。彼の一生は勝利を目的として戦わず、別に大いに企図するところがあり、空を撃ち虚を狙って、空の空なる事業をなして、戦争の中途でいずこかへと去ることを常とする者があるのである。
このような戦いは、文士が好んで戦うもの、文士はこのような戦いに運命を委ねているのである。文士の前にある戦場は、局地的な原野ではなく、広大な原野である。彼は事業をととのえて帰ろうとして戦場に赴くのではなく、必死を期して、野原の露となることを覚悟して家を出るのである。このように戦場に出て、このような戦争をするのは、文士が兵馬の英雄とは異なる理由であり、事業の結果に大いに相異なる現象を表すのもこのためである。
愛山君が、文章がすなわち事業であると宣言したのはよいが、文章と事業とを都会の家屋のように互いに接近しているように言ったのはだめである。あえてだめという。なぜならば聖浄にして犯すべからざる文学の威厳は、事業という俗界の神に近づけられたことによって毀損されるはずだからである。八百万の神々の中で事業という神の地位は全然高くないのである。文学という女神は、あるいはオールドミス(老嬢)にて世を送ることがあるとしても、卑俗な神とめあわされることを承諾しないはずだからだ。
山東京山、柳亭種彦、曲亭馬琴の三文士を論じて、京山を称揚したのは愛山君である。その理由はなぜか。馬琴は己れの理想を歌って馬琴の文学を衒っているに過ぎず、当時の社会を知るのに役に立たない。種彦は人品高尚で俗情に疎いところがあり、平民に縁が遠いのでよくない。独り京山になると、番頭小僧までも余すことなく写実しているので重んずべきである。このように愛山君は説いた。天下の衆生を残らず愛山君のような史論家にさせると、当時の社会を知るという点を重視して、京山をも、西鶴をも、最上の作家として畏敬するに違いない。天下の衆生を残らず愛山君のような平民論者にさせると、山東家[京伝、京山]の小説がすべての他の小説をしのぐとすることに必ずなるだろう。
されど文学は事業を目的とするものではない。文学が人生に関連することが、京山の写実主義と同じほどであることを必須とはしないのである。文学が敵を目掛けて撃ちかかることが、山陽の勤王論と同じほどであることを必須としないのである。最後に、文学は必ずしも一人もしくは数百人の敵、見るべき敵を目掛けて撃つことを必要としないのである。「撃」という字は山陽という一流の文士には用があるが、愛山君が言う空の空を目掛けて大いに撃つ文士に、何の用があるだろうか。山陽も撃った、山陽の撃った戦いは、今日人に記憶されている。されどその撃ったところは、愛山君の言うように直接に人生に関連している。人生に関連しているがゆえに、人生を離れることもまた速やかだろう。源頼朝はよく撃った、されどその撃ったところは速やかに去った。彼は一個の大戦士であるが、彼の戦場は実に限りのある戦場であった。西行もよく撃った、シェイクスピアもよく撃った、ワーズワースもよく撃った、曲亭馬琴もよく撃った、これらの人々も大戦士である。そうして前者と相異なる理由は、前者のように直接の敵を目掛けて限りある戦場で戦わず、換言すれば天地の限りのないミステリーを目掛けて撃ったがゆえに、愛山君には空の空を撃ったと言われたが、空の空の空を撃って星にまで達しようとしたのである。鎌倉山に行って頼朝の墓を開いて見よ。彼が言わんとしていることは何であろうか。西行の姿を『山家集』の上に来て見よ。どちらがうまく言い、どちらがうまく言わないのか。されど愛山君は、文士は世間の役に立たなければならない、西行や馬琴の徒が何の役に立っただろうかと問うだろうか。
文学の活用論は、今日に始まったのではない。我々の先祖に勧善懲悪説があり、我々の同時代に平民的批評家としての活用論者を、愛山君に得たのも理由がないわけではない。ガラスは水晶に比べて活用の便がある、もって窓を装い、もってランプのホヤにすることができる。天下はあまねくその活用の便を認めうるのである。されど天下の愚人が水晶という活用の便が乏しいものに、高額を払うのはなぜか。私は疑わない、水晶を買う者に、金数十円を出して露店のガラス玉を買わせるという神学を創建する者があれば、水天宮に参詣する衆生が争ってその説法を聴聞するにちがいないと。京山を、山陽をこの神社の偶像とすれば、カーライルに『英雄崇拝論』の一章で取り上げなかったことを、地下で後悔させるにちがいない。
吉野山に遊覧して、嘆息する者がいる。「どうして桜の木を切って梅の木を植えないのか、桜の木はどんな活用に適するところがあろうか、梅の木を植えて果実で千金の利益を得るのに及ぶことがあろうか」と言う。一人が傍らから口を出して、「梅の木は得る利益がサツマイモを作るのに及ばない」と言う。他の一人はまた、「サツマイモは市場での相場が極めて廉価である、アメリカ種のリンゴを植えるのに及ばない」と言う。私はこれらの論者の利益計算に速やかであることを喜び、真理を認めることの確かなことに喜んで感謝したいと思う。されど吉野山を活用論者の手に委ねるのは、福沢諭吉先生を同志社の総長に推すことを好まないのと同様に好まないのである。
肉体の力は、肉体の力を撃つのに十分である。「死んだ者は死んだ者を葬ることができる」という真理は、ナザレ人の子キリストもこれを説いた[「死者をして死者を葬らせよ」(マタイ8-22)]。されど死んだ者で葬れない者があるのは、肉体の力では撃破できない者があることともに、他の一側面に横たわる真理である。一人の敵を倒す法[剣術]を学ぶのでは十分ではないことは、万人の敵を倒す兵法を学んでもなお失敗した項羽すら、これを発見した。一万人の敵を倒す兵法を学ぶことは、百万人の敵を倒す兵法を学ぶことに及ばないからであろう。百万人の敵を倒す兵法を学んだ(仮定して)高祖劉邦も、また「死朽」という数えられない敵の前には、無言で倒れたのである。「死朽」という敵に対して、我々は我々の刀剣を振るうこと、愛山君の言う英雄が剣を振るうようにしても、勝負の運命は初めから定まっているように、我々は(力としての)自然の前に立つと脆弱な勇士なのである。
「力としての自然」は、目に見えない銃鎗、言い換えると空の空なる銃鎗で、時々刻々と肉体としての人間に迫って来るのである。草薙の剣は、目に見える野火をうまく薙ぎ尽したけれど、見えざる銃鎗はよもや薙ぎ尽せないだろう。英雄に剣を振るわせるのは、見える敵に当たればこそである。文章を京山もしくは山陽のように世間の役に立たせるため、人生に関連させるために戦わせるのは、見える「実」(すなわち敵)に当らせるためである。されど空の空なる銃鎗を迎えて戦うには、空の空なる銃鎗でしなくてはならない。ここに霊の剣を鋳る必要があるのである。
自然は我々に服従を命じるものである。力としての自然は、我々を暴圧することをためらわないものである。「誘惑」を向け、「欲情」を向け、「空想」を向けて、我々をほとんど孤城落日の地位に立たせることを好むものである。そうして我々はある程度までは必ず服従せざるを得ない「運命」、そう、悲しき「運命」に包まれているのである。項羽はうまく虞美人と別れることができたけれども、我々はこの悲しき「運命」と一刻も別れることができないのである。されど自然は我々を「失望落魄」の極み、ついに甘んじて自然の力に服従しつくすまでには、我々を困窮させないのである。ここに活路がある。活路は必ずしも活用と趣を一つにはしない。空虚な英雄を気取って、力としての自然の前で大言壮語するのは私の言う活路ではない。我々は我々の霊魂をして、肉体として我々の失った自由を、他の大自在の霊世界に向かってほしいままに握らせることができるのである。自然は、暴虐を第一とする兵馬の英雄のようではない。一方で風雨や雷鳴電光を駆りたてて我々を苦しめると同時に、他方で美妙で絶対的なものを表わして我々を楽しませるのである。風に対しては戸を造り、雨に対しては屋根を葺き、雷に対しては避雷柱を造る。このように人間はできるだけ物質的な力で自然の力に当たるべきであるが、こうするのは限りある力で限りなき力を撃つという業であって、限りある力を投げすてて自然の懐の内に躍り入ることの絶妙さには到底及ばないのである。ここで吉野山は、活用論者には見やすくはない活機[活動の源泉]を我々に教えるのである。「願はくは花の下にて春死なむ、そのきさらぎの望月のころ」と歌った詩人西行が、活用論者の知ることができない大活機を看破したのは、ここである。
宗教がない崇高さがないとあざけられた芭蕉は、振り向いてあざけった者を見もしまい。されどこのようにあざけった平民的な短歌の史論家(同じく愛山君)と同時代に立つ悲しさから、無言勤行の芭蕉からその詩句の一つを借りて、我が論陣を固めるという非礼を行わざるをえない。古池の句は世に定説があると聞くのでこれを引かず、一層簡明な一句、私の浅学に該当するものがあるので、暫らくこれを論じようと思う。「明月や池をめぐりてよもすがら」の一句である。
池の岸に立つ一個人は肉体をもって成り立つ人間であることを記憶せよ。彼はすべての愛情による束縛、すべての執着、すべての官能的感覚に囲まれていることを記憶せよ。彼は限りある物質的な力で争うことができる限りは、これら無形の仇敵と格闘したことを記憶せよ。彼は功名と栄達と事業とに手を出す多くの機会があったことを記憶せよ。彼は人生に関連する事業に何にも難しいことはなかったことを記憶せよ。そうであるのに彼は自ら満足することができなかった、自ら勝利を占めたと信じることができなかったのである。浅薄な眼光では勝利と見るべきものをも、彼は勝利と見ることができなかったのである。ここで彼は、「実」を撃つ手を休めて、「空」を撃とうとしてもがき始めたのである。彼は池のそばに立って、池の一小部分を睨むことに甘んじることなく、徐々に歩みはじめたのである。池の周辺を一巡し、一巡では池の全面を睨むのに十分ではないことを知って、再び巡回した。再巡回は池の全面を睨むには十分であったけれど、池の底までは睨むことができなかった。それゆえにさらに三回、四回と巡り、そうしてついに夜もすがら巡ったのである。池はすなわち「実」である。そうして彼が池を睨んだのは、暗中で水を打つ子供の業と同じではなく、何かを池に写して睨んだのである。何かを池に打ち入れて睨んだのである。何かに池を照らさせて睨んだのである。「睨んだ」とは、当初に見る仕方を指して言うことができる言葉である。後に見る仕方を言う言葉は消滅(annihilation)の他にはないだろう。彼は「実」を忘れたのである、彼は人間を離れたのである、彼は肉体を脱したのである。「実」を忘れ、肉体を脱し、人間を離れて、どこかに去る。ホトトギスの行方は問うことを止めよ。天涯高く飛び去って、絶対的なもの、すなわちイデアにまで達したのである。
彼は事実の世界を忘れたのではない、池を両三回巡るのは「実」を見抜く心があるからである。「実」は自然の一側面であり、そうして「実」を照らすものもまた自然の他の一側面である。「実」は我々の敵となって我々に迫ったが、他の一側面である「虚」は、我々の良い友となって、我々を導いて天涯にまで上らせるのである。池面に映りでた真ん丸い明月は、彼に力としての自然を後方に見て、一躍して美妙な自然に進み入れさせた。
崇高[sublime]とは形の判断ではなく、「想」の領分である。すなわち前に言った「池をめぐりてよもすがら」したような人が、一躍して自然の懐の内に入った後に、彼の場所で見出すべき友人を言うのである。この至真で至誠な友人を得て、その後、夜を徹するまで池を巡ることに味があるのである。池を巡るのは無(nothingness)を巡るのではない、この世ならぬ友人とともに、散歩遊びを楽しむためにするのである。
造物主は我々に意志の自由を許す。現象世界[実界、実世界]で煩悶苦戦する間に、我々は造物主が我々に与えた大活機を利用して、猛虎の牙を弱め、倒崖の根を堅くできるのである。現象以外に超脱して、最後の理想に到着する道が、我々の前に開けている。大自在の風雅を伝道するのは、この大活機を伝道することである。どうして英雄が剣を振るうと言うのか。どうしてなす所があるためと言うのか。どうして人生に関連しなくてはならないと言うのか。空の空の空を撃って、星にまで達することを期すべきである。俗世には俗世が笑うままに笑わせればよい、俗世を救済するのは俗世に喜ばれるためではない。肉体の剣がどれほど鋭くとも、肉体で肉体を撃つのは文士の最後の戦場ではない。眼を挙げて大大大の虚界[想世界]を見よ。彼の場所に登攀して清涼宮を捉えよ、清涼宮を捉えたら携えて帰って、俗界の衆生にその一滴の水を飲ませよ。彼らは生きるだろう。ああ、彼らが生きることを切に望む。
自然の力にほしいままに私の脚のすねを縛りつけさせよ。されど私の頭部は大勇猛の力で、現象以外の別天地にまで身を伸ばして立たせ、そこを大自在の風雅と散歩させよ。彼の物質的論客のような者は、世界を狭苦しい家屋にして、その家屋の内部を整頓する他にはなすべき一生の仕事はないとし、甘んじてここで起居しようとする。そうして風雨が外より犯す時、雷鳴と電光が上より襲う時に、恐怖に慄然とすることを自らの運命として諦めようとする。霊性的な道念を散歩する者は、世界を世界大のものと認めることを知る。そうして世界大の世界を満足自足すべき住宅とは認めないのである。世界大の世界を離れて、大大大の実存を現象世界以外に求めて止まないのである。物質的英雄が煌々と輝く利剣を振るって、狭苦しい家屋の中で仇敵と接戦する間に、彼は大自在の優れた力を懐にして無言で座っているのである。
悲しき限界(limit)は人間の四面に鉄壁を設けて、人間を卑俗な一生涯から脱することができないようにしている。鵬の大をもってしても蝉の小をもってしても、同じくこの限界を破ることはできないのである。そうして小さな蝉が自らその小であることを知らず、大きな鵬が自らその大であることを知らないのと同様に、限界に縛られていることを知らずに欣然と自足するのは、憐れむべき自足である。この憐れむべき自足をもって現象世界に身をおいて、快楽と幸福とに欠けるところがないと自ら信じる者は、浅薄な楽天家である。彼は狭苦しい家屋の中で、物質的論客と同席して泰平を歌おうとする。歌え、汝が泰平の歌を。
されどこのような狭い家の中では、味もない「義務」が双翼を張って極めて得意になるのである。剛健な「意志」はその脚を失って幽霊に化けるのである。訳もない「利他主義」が荘厳な黄金仏となって礼拝されるのである。「事業」という工匠は唯一の左甚五郎になるのである。「快楽」という食卓は最良の哲学者になるのである。「衒学」という巨人は、屋根裏を突き上るほどの英雄になるのである。すべての霊性的生命はここを辞去すべきである。人間をことごとく木石の偶像にさせる究極の社殿は、この狭い家であろう。この狭い家の内では、菅原道真は失敗した統治者、松尾芭蕉は意気地のない遁世家、曲亭馬琴は些末な非写実文人、西行は無欲な閑人となるのである。新井白石のような、頼山陽のような、足利尊氏のような、仰向きに見上げるべきなのは、これらの事業家の他にいないように必ずなるだろう。
頭をあげよ、そうして見よ、そうして求めよ。高遠な虚想で、真に広々とした家屋、真に快美な境地、真に雄大な事業を見よ。そうして求めよ、汝の切望(longing)を空の果てに投げよ。空の果てより、汝が人間のためになすべき天職をとってこい。ああ文士よ、どうして縮こまって人生に関連することを追求しようとするのか。
(明治二十六年二月、「文学界」二号)

