過去に悲惨な出来事があって世をすねた怪物みたいなキャラの、過去を具体的に掘り下げたら、ただケツの穴の小さい小人物みたいになっちゃう場合もありますねw
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
歯舞群島の島の名前が面白いのでメモしておく。
「水晶島」「貝殻島」「海馬島」は小説に出てきそうな名前である。いずれ私が使うかもしれない。
「水晶島」「貝殻島」「海馬島」は小説に出てきそうな名前である。いずれ私が使うかもしれない。
| 日本語 | ロシア語 | 英語 | 島名の由来となったアイヌ語 |
|---|---|---|---|
| 海馬島 とどじま |
Осколки オスコルキ島 |
Oskolki | |
| 多楽島[* 13] たらくとう |
Полонского パロンスキー島 |
Polonskogo | 「トララ・ウク(皮紐・取る→皮紐を取る島)」 |
| 志発島 しぼつとう |
Зелёный ゼリョーヌイ島 |
Zelyony | 「シペ・オッ(鮭・群在する所)」 |
| 勇留島 ゆりとう |
Юрий ユーリ島 |
Yuri | 「ユウロ(それの鵜がたくさんいる→鵜の島)」または「ウリル(鵜の島)」 |
| 秋勇留島 あきゆりとう |
Анучина アヌーチナ島 |
Anuchina | 「アキ・ユリ(弟・勇留→勇留の弟)」 |
| 水晶島 すいしょうじま |
Танфильева タンフィーリエフ島 |
Tanfilyeva | 「シ・ショウ(大きい・裸岩)」 |
| 貝殻島 かいがらじま |
Сигнальный[* 14] シグナリヌイ島 |
Signalny | 「カイ・カ・ラ・イ(波の・上面・低い・もの<岩礁>)」 |
PR
短編漫画、あるいは映画脚本ネタ
大学生のサークル仲間が男女数人で旅行をする。
そのうちの一人が旅行の様子をずっとビデオ撮影している。
旅行最終日、宴会をする、その様子を撮影中に撮影者は酔っぱらってビデオを片隅に置いたまま寝室(他の部屋)に行って寝る。ところが、ビデオのスイッチを切り忘れ、ビデオは廻ったまま、部屋の様子が撮影され続ける。
後は、撮影されていることに気づかず、残った連中は、その場にいない人間の悪口で大盛り上がり、果てには、その場にいない人間の恋人(女)が、残っていた連中と大乱交。
(映画なら、途中途中で、ビデオの「銃口(カメラアイ)」の画像が挿入される。「2001年宇宙の旅」のハルがボウマン船長らの「悪だくみ」を「見ている」シーンのように。)
(追記)ちなみに、これです。
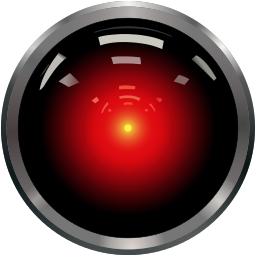
最後のシーンは、翌日になって、「撮影係」が宴会の場のビデオを見つけて、「まだ動いている。ちぇっつ、電池の無駄遣いしちゃったなあ」というシーンで終わるか、あるいは、その撮影内容を自分で見て顔を青ざめさせるシーンか、或いは後日、みんなで「旅行の思い出ビデオ」鑑賞会をしているシーンで終わってもいい。
なお、宴会の場で、先に酔いつぶれてその場で寝ていて、ふと目が覚めた時に「友人」による私への悪口を聞いたのは私自身の経験。起きるに起きられず弱ったが、自分の「友人」の本心、あるいはその正体を知ったのは衝撃だった。また、組織の上役であった時に、隣室に私がいることも知らず、部下のひとり(私にいつもおべっかを使う人間だった)が私の悪口を言っているのを聞いたこともある。まあ、考えれば、自分だって「表の顔」と「裏の顔」を持っているわけだが、なぜか他人(特に友人や部下)の「表の顔」をつい信じ込むのが人間の愚かしさなのだろう。
大学生のサークル仲間が男女数人で旅行をする。
そのうちの一人が旅行の様子をずっとビデオ撮影している。
旅行最終日、宴会をする、その様子を撮影中に撮影者は酔っぱらってビデオを片隅に置いたまま寝室(他の部屋)に行って寝る。ところが、ビデオのスイッチを切り忘れ、ビデオは廻ったまま、部屋の様子が撮影され続ける。
後は、撮影されていることに気づかず、残った連中は、その場にいない人間の悪口で大盛り上がり、果てには、その場にいない人間の恋人(女)が、残っていた連中と大乱交。
(映画なら、途中途中で、ビデオの「銃口(カメラアイ)」の画像が挿入される。「2001年宇宙の旅」のハルがボウマン船長らの「悪だくみ」を「見ている」シーンのように。)
(追記)ちなみに、これです。
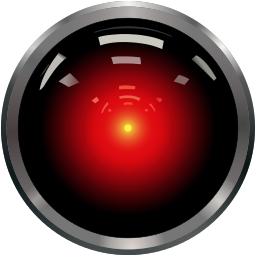
最後のシーンは、翌日になって、「撮影係」が宴会の場のビデオを見つけて、「まだ動いている。ちぇっつ、電池の無駄遣いしちゃったなあ」というシーンで終わるか、あるいは、その撮影内容を自分で見て顔を青ざめさせるシーンか、或いは後日、みんなで「旅行の思い出ビデオ」鑑賞会をしているシーンで終わってもいい。
なお、宴会の場で、先に酔いつぶれてその場で寝ていて、ふと目が覚めた時に「友人」による私への悪口を聞いたのは私自身の経験。起きるに起きられず弱ったが、自分の「友人」の本心、あるいはその正体を知ったのは衝撃だった。また、組織の上役であった時に、隣室に私がいることも知らず、部下のひとり(私にいつもおべっかを使う人間だった)が私の悪口を言っているのを聞いたこともある。まあ、考えれば、自分だって「表の顔」と「裏の顔」を持っているわけだが、なぜか他人(特に友人や部下)の「表の顔」をつい信じ込むのが人間の愚かしさなのだろう。
これはわりと理にかなっている創作法だと思う。漫画だけでなく、小説にも脚本にも言えるのではないか。で、そのクライマックスをだいたい「起承転結」の「転」に持ってくるのが通常のやり方で、時には最初にクライマックスを持ってきて観客を驚かせるなども映画などにはあるようだ。ただし、その場合は中盤から終盤まで観客は退屈なシーンを延々と見せられることになる。やはり、「起承転結」はドラマの黄金律だと思う。
なお、小論文指導をしていた経験から言うと、多くの生徒の書く小論文の最初の4分の1くらいは実につまらない、どうでもいい前置きなので、書き上げたら思い切ってその冒頭部を全部カットすると、切れ味のいい小論文になる。余計な前置きは要らないのである。
なお、小論文指導をしていた経験から言うと、多くの生徒の書く小論文の最初の4分の1くらいは実につまらない、どうでもいい前置きなので、書き上げたら思い切ってその冒頭部を全部カットすると、切れ味のいい小論文になる。余計な前置きは要らないのである。
【初心者向け】
まず何ページになってもいいからネームを完成させる→その作品でいちばん面白いシーンを1つ選ぶ→そのシーンに関係ないところをばっさりカットする→クライマックスのある読み切り完成!
なかなかネームが完成しない人は、設計と工事を同時にやるからです。建ててから壊せばOK。
確か、萩原(荻原だったか?)朔太郎が、「なぜ詩(小説なども含むか?)を書くのか」という質問に、簡潔に「復讐」と答えたという話があるようだが、下の北村薫の言葉も同じことだろう。つまり、ままにならない自分の実人生や、それをそういうようにさせた存在(神、創造主)への「復讐」であり、「抗議」であるわけだ。
私は、好きなゲームは何周もする人間だが、2周目や3周目のほうが、気楽に楽しめるのである。1周目は、「何がどうなっていくのか分からない」という不安感と共にプレーしているので、スリリングで面白い反面、「楽しさ」にはむしろ欠けるわけだ。
こういう、「2周目」的な感じは、「実人生から降りて小説世界を楽しむ」感じに似ている。実人生の苦痛や恐怖は、小説世界では単なる刺激物になり、成功感や高揚感は実人生同様に味わえるわけだ。いや、むしろ、現実人生よりも「高度な人生」が味わえるのである。我々の日常に、トルストイやドストエフスキーやバルザックやデュマの登場人物のような存在が有り得るだろうか。
最近のゲームは2周目以降に、1周目で得た経験値や道具などを持ちこして、「強くてニューゲーム」というシステムがあるらしいが、「なろう小説」の大半は、「強くてニューゲーム」精神で書かれているのではないだろうか。
(以下引用)
私は、好きなゲームは何周もする人間だが、2周目や3周目のほうが、気楽に楽しめるのである。1周目は、「何がどうなっていくのか分からない」という不安感と共にプレーしているので、スリリングで面白い反面、「楽しさ」にはむしろ欠けるわけだ。
こういう、「2周目」的な感じは、「実人生から降りて小説世界を楽しむ」感じに似ている。実人生の苦痛や恐怖は、小説世界では単なる刺激物になり、成功感や高揚感は実人生同様に味わえるわけだ。いや、むしろ、現実人生よりも「高度な人生」が味わえるのである。我々の日常に、トルストイやドストエフスキーやバルザックやデュマの登場人物のような存在が有り得るだろうか。
最近のゲームは2周目以降に、1周目で得た経験値や道具などを持ちこして、「強くてニューゲーム」というシステムがあるらしいが、「なろう小説」の大半は、「強くてニューゲーム」精神で書かれているのではないだろうか。
(以下引用)
「小説が書かれ読まれるのは、人生がただ一度であることへの抗議からだと思います」という北村薫の言葉が、とても好きです。選ばなかった、選べなかった、与えられなかった、たくさんの「もしもの世界」に、小説を読み、また書くことで、私たちはいきられるのだと思う。
プロフィール
HN:
冬山想南
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
P R


