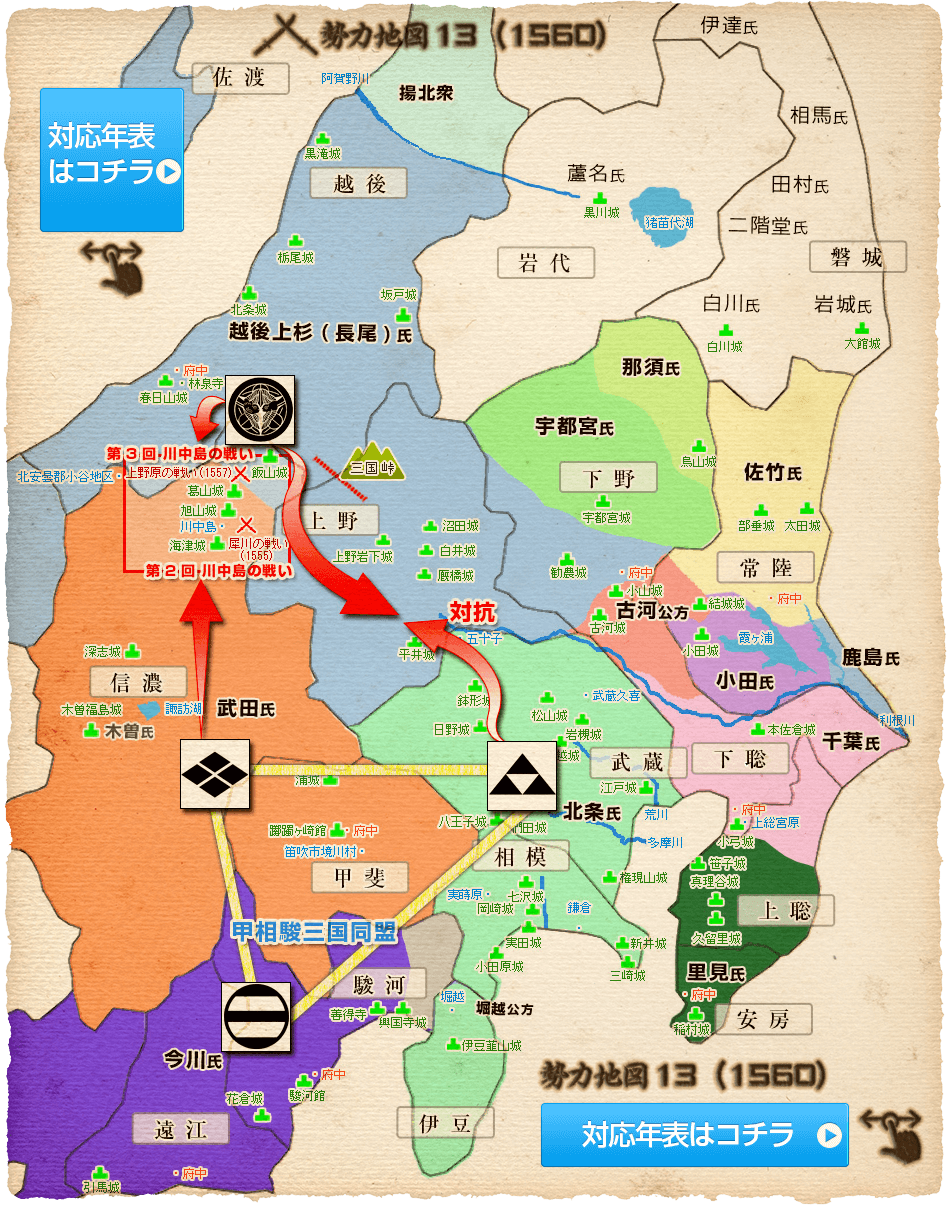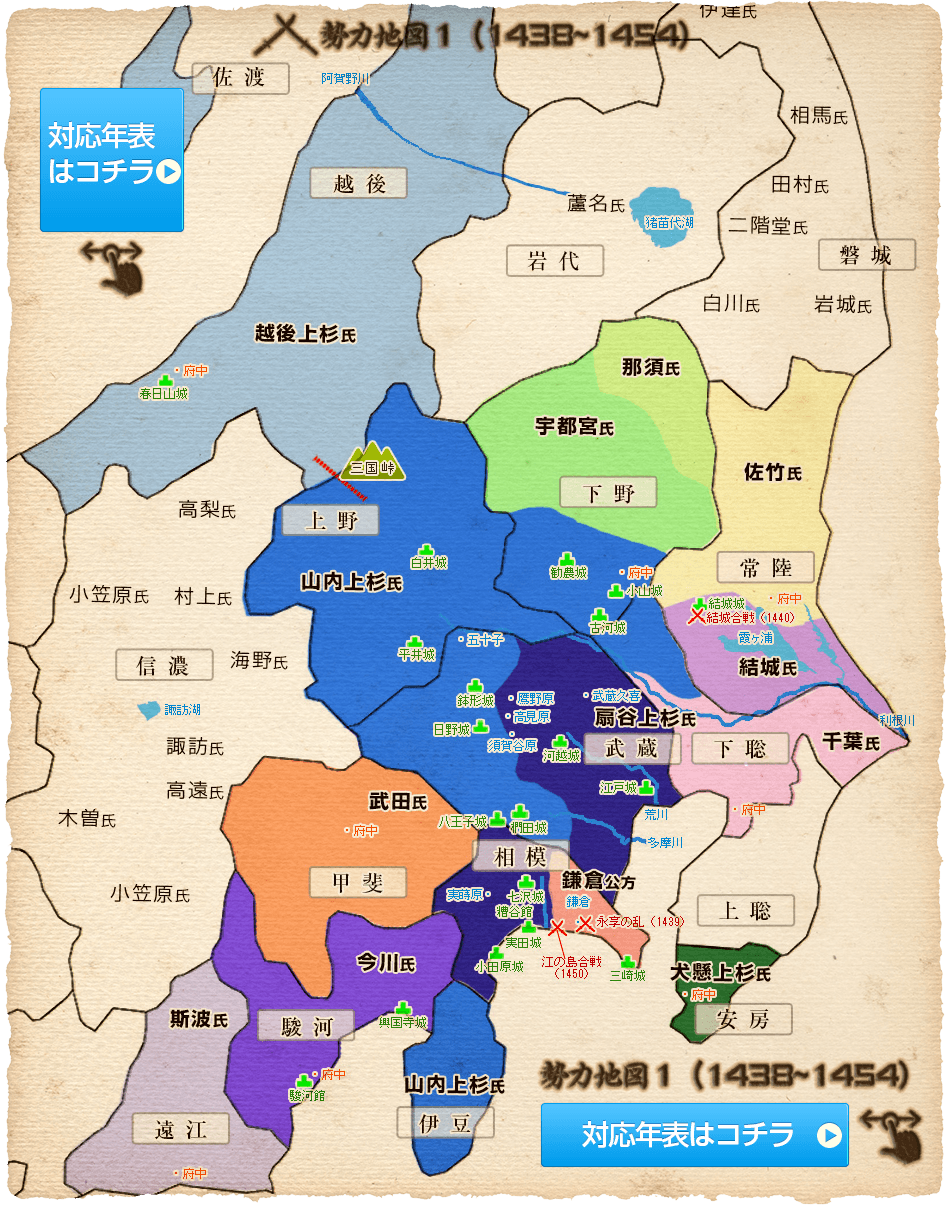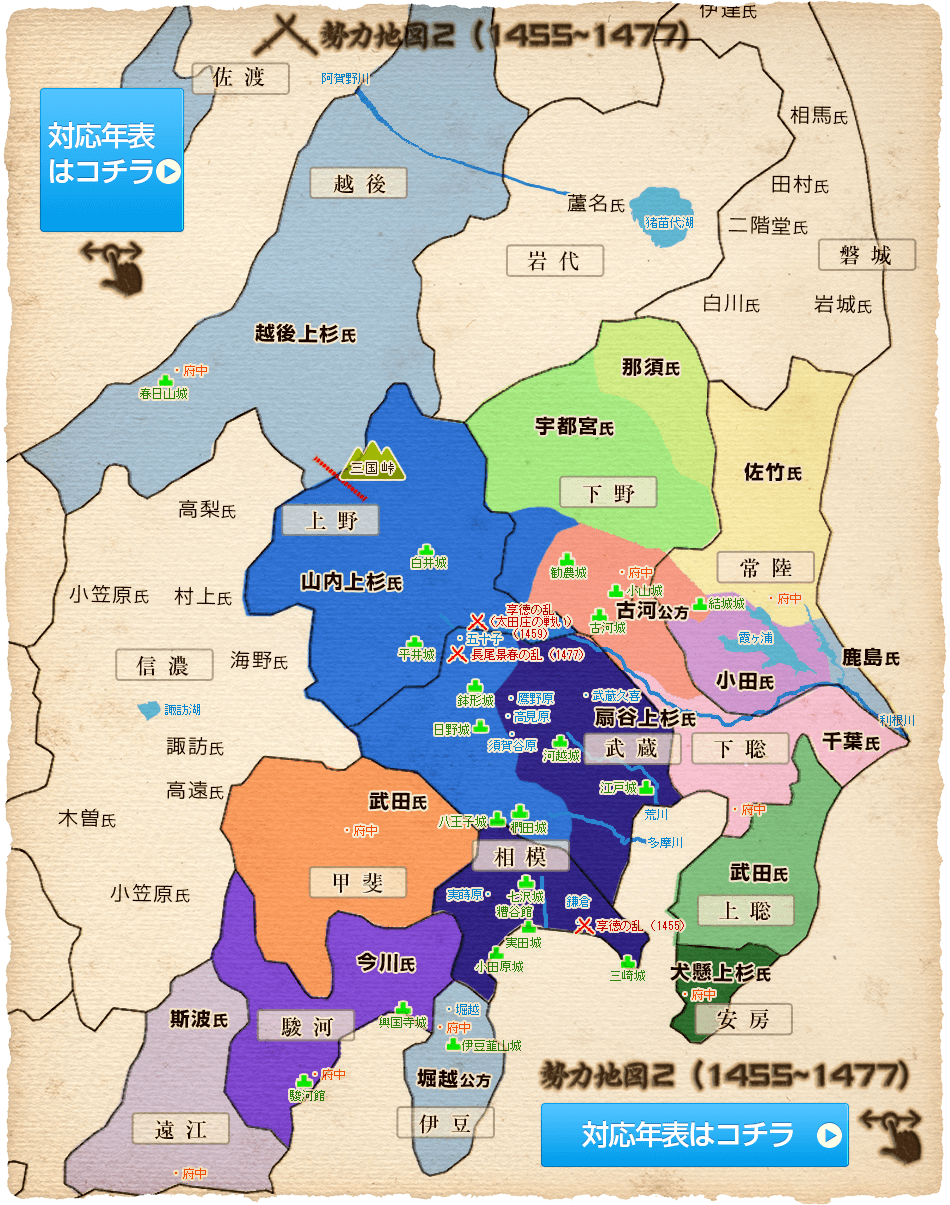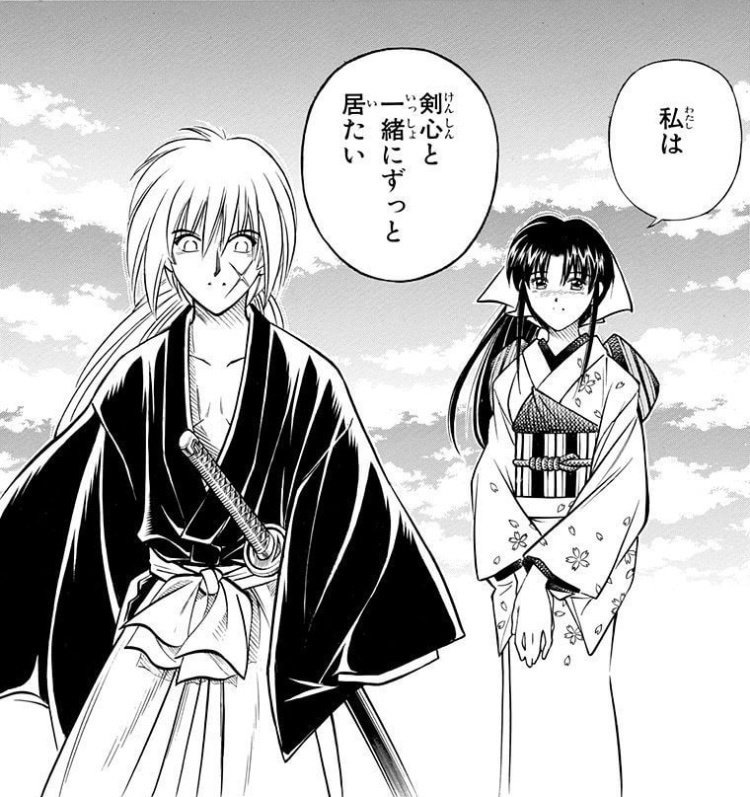ふと、大杉栄の娘で、「魔子」という名前が有名な大杉魔子はどのような人生を送ったのか気になって調べると、とある書評が検索された。書評と言うより、本の要約に近いが、そのほうが「事実」が浮かび上がっていい。
松下竜一著 『ルイズ 父に貰いし名は』
関東大震災後の混乱に乗じ、甘粕正彦ら憲兵は大杉栄、伊藤野枝、そしてまだ六歳だった大杉の甥っ子の橘宗一を虐殺する。
著者は1980年から1年半に渡り大杉の娘ルイズにインタビュー取材をし、ルイズを中心とした大杉、伊藤の遺児たちの姿を描いている。
大杉、伊藤は長女に「悪魔の子」と呼ばれたからと挑発的に魔子と名づける。その後誕生した子どもたちは、エマ、ルイズ、ネストルとアナキストたちから名前が取られた。
子どもたちは無戸籍だったが、両親を失った後に戸籍を作る際に真子、笑子、留意子、栄と改名されている(栄は一歳で病死してしまう)。なお「エマ」は二人いて、次女のエマは生まれてすぐに大杉の妹に「さらわれるようにして」養子に取られ幸子と改名され、三女に同じエマという名前をつけている。幸子は自分の両親が大杉と伊藤だということにある時期まで気づくことはなかったという。
笑子と留意子は福岡の今宿の伊藤の実家で育てられることになる。真子は一時伊藤の叔父にあたる代準介の家から学校に通っていたが、結局大杉の弟勇に引き取られることになる。
遺児たちの中で最も注目を浴びていたのが長女の真子だった。遺児たちを養子に迎えたいとする手紙が多く寄せられたが、とりわけ真子を希望する者が多く、代家には今でもその手紙が残っており、本書に引用されている。
真子、いや「魔子」を誰よりも強く思慕していたのは大杉の同志たちだった。大杉は魔子を溺愛しており、フランスで獄中にあったときに魔子に向けて歌を作ったことはその自叙伝の有名なエピソードである。同志たちは頑ななほどに「真子」ではなく「魔子」と表記し続けたのも、大杉を思えばこそであり、また大杉の死後に「魔子をいきなり田舎に攫われてしまった」という気にもさせられた。真子が横浜に住む勇に引き取られることになったのも、同志たちが望めばこそだったのかもしれない。大杉と伊藤が虐殺された時にすでに物心ついており、両親をはっきりと記憶している魔子という存在はアナキストたちにとって一縷の希望であったのだろう。
大杉の報復に失敗し獄中にあった和田久太郎は死を予期し、「身近な同志たちに「久太漫評」を依頼したのだが、依頼名簿の中で大杉魔子には「特に書いてほしい者」という意味の△印が付されている」そうだ。まとめられた『獄窓から』には当時九歳の魔子の手紙が収録されている。
久さんへ 大杉マコ
久さんと最後にあつた時から、もう二年になりますね。久さんのことは大がい忘れたけれど、久さんは、よく手をうしろへまはして頭をかく癖だけ一つおぼへてゐます。/悪いでせう、あの監獄であつた時、何にか言ほうかと思つたけれど、口がつぐんで何にも言へばかつたので。ごめんなさい。私も、久さんみたいに、童謡がうまいのよ。それでは一つ聞いててふだいね。そして真子自作の童謡が書かれている。
魔子が漢字が書けるようになったことを喜び、またその運命を痛々しくも思い同情し、その成長を気にかけ、自作の童謡も書き送っていた和田は、この子どもらしく可愛らしい手紙を読んで何を思ったのだろうか。この手紙の翌年、和田は独房で首を吊る。
笑子と留意子は伊藤家で、叔父や親戚のお兄ちゃんたちに囲まれて素朴な田舎暮らしを平和に楽しんでいるかのようなエピソードもあるが、そこには不吉な影もさしている。二人が着ていたハイカラな服は田舎ではまず見られないもので、実際は大杉の同志たちが遺児たちに贈り物をしていただけなのだが、ロシアから金が送られているせいだと噂された。
そして二人が学校に通うようになると、好奇なものや悪意のこもったものなど様々な視線にさらされることになり、中には直接にあてこすりをする教師もいた。留意子は「天皇陛下」という言葉を聞くたびにびくっとなり、次第に相手が両親のことを知っているのかどうか、両親の話題に触れるのかどうかについての「本能的嗅覚」を身につけるようになる。
祖父の葬儀に真子がやって来た。姉妹の十年ぶりの再会であったが、パーマをかけるなど都会風に洗練され、また未だ記者たちが押しかけてくる有様だったが自分の正体を隠すことなく堂々と取材に応じる真子は、妹たちには遠い存在に映った。しかし真子も、好奇の視線や同志たちからの期待といった重圧を軽く受け流していたわけではなかった。学生時代をふり返った文章が残っている。教師たちからは常に「カンシ」され、読みたい本も読めず、上の学校へ行きたかったが「学問をさせないほうがあぶなくない」と止められ、それでいて就職先もなかなか見つからなかったということが記され、その孤独が浮かび上がってくる。妹たちは真子について、笑い上戸のように陽気でありながら「ある一線より内へは決して踏み込ませない」、「決して心の奥を打ち明けぬ人」という印象を抱くことになる。
真子が祖父の死後に福岡に住むことにしたのも、妹たちの面倒を見たいからというよりも東京から逃れたいという思いがあったのかもしれない。
大正から昭和、そして戦争の時代にあのような出自を抱えて生きる留意子の人生は「朝ドラ」のように見えてしまえるようなところもある。もっとも、「朝ドラ」の範疇を軽く踏み越えるもので、絶対にドラマ化されるものではないだろうが。
ある日、「特徴ある学帽から慶応義塾の学生であることがすぐにわか」る若者が留意子に大杉と伊藤の墓はどこにあるのかと尋ねた。すでに二人の存在は禁忌になろうとしていた時代だ。墓(といっても荒らされるために石を置いただけのものだが)に案内すると、この若者は留意子の写真を撮り、よかったら現像して贈るので住所と名前を教えてほしいと言う。留意子が教えると、この若者は相手が大杉と伊藤の遺児であることに始めて気づくのであった。二人は文通を始める。留意子にはこれが恋なのかどうかはわからなかったが、二人が互いに好意を抱いていたことは間違いないだろう。しかし留意子は、慶応の学生で将来有望であろうこの若者と自分が一緒になるべきではないと心を決める。退役軍人と結婚を決めたことを手紙で知らせると、相手はただゲーテの『若きウェルテルの悩み』についての本を送ってきただけだった。その扉には、「いつもの端正なペン字で<永遠の友愛をこめて、留意子様に贈る>」とだけ書かれていた。
留意子も東京に出て大学へ行きたいという希望を抱いたこともあったが、学資にあてるはずだった大杉や伊藤の著作は最早売れるような時代ではなく、印税は途絶えてしまう。また遠慮がちな性格もあり、タイプを学んで就職することに決めるが、ここでも「主義者」の娘であることを痛感させられる出来事にいくつも遭遇する。姉の笑子の結婚もこの生まれのせいで破綻してしまうほどだったが、留意子に熱烈に求婚する男が現れる。相手の実家からは勘当されてしまうが、留意子は王丸和吉と結婚することになる。
和吉は、あの満州で仕事を得ることになる。両親を殺したあの甘粕が強大な権力を握る傀儡国家にである。先に出発していた夫の後を追うが、道中で不審な出来事が頻発する。明らかに尾行をされており、その行動は逐一監視されていたようだ。
留意子が満州でショックを受けたのは、日本人の子どもが中国人の苦力を下品に罵るなど、中国人や朝鮮人に対する差別であり、また和吉を含むほとんどの日本人がそのことを気にすらかけていないことだった。
留意子が銭湯に行くと男が女の背中を流していたので慌てて引き返すという出来事があった。和吉は「馬鹿だなあ、あれは中国人なのに」と言い、周囲もどっと笑った。和吉も周囲も中国人を「人間」扱いしていないことが表れている。さらに銭湯ではこんな出来事もあった。いずれも16,7歳かという若い女性たちが20人ほど数珠繋ぎのように入ってきた。みな痛ましいほど痩せていて、誰一人として笑う者はなく、まるでお通夜のような表情だった。そして先客たちは汚いものに触りたくないとでもいうように、そそくさと出て行った。和吉は「ああ、それは前線の慰安婦だ。おおかた国境から帰ってきたのだろう」とこともなげに言った。留意子は慰安婦の存在を知っていたが、その姿を目の当たりにし、また和吉を含む男たちの暴力性に直面しさらに苦悩は深まる。
追い討ちをかけるようなことが、幼い頃の遊び相手だった従兄の良介との再会にまつわる出来事だった。前線除隊し、天津に残っていた良介は華北への輸送貨物車の護衛の仕事中に、近くに来たからと立ち寄った。別れの際に駅まで送っていくと、良介は「金にはなるんだが人間のする仕事じゃないね」と言った。そして「留意ちゃん、貨車の中を見ていかないか。――こういうものを見ると、“王道楽土”満州というものの正体がわかるから」、と続けた。
貨車からは悪臭が漂っていた。留意子は思わず死体運搬車かと思ったが、中にいるのは生きている人間だった。「密山炭鉱まで運ぶんだが、なにしろ十日がかりだからね。着いたときには、死ぬ者も相当に出ているんだろうな」と良介は耳元で囁いた。留意子は「動いていないと見えた者たちの視線が、自分たちの方に向けられていると気づ」き、逃げるように貨車を離れた。
その後夫婦は日本に戻り、敗戦を迎えた時留意子は妊娠していた。博多湾に米軍が上陸するという噂が流れると、「女、子供」はいっせいに避難を始めた。留意子は「いくら米軍でも、妊婦をどうこうしないでしょうもん」と言うと、和吉は「お前は戦争というものを知らんから、そんな呑気なことをいう」と語気を強めた。「戦争というものは、人間を鬼にしてしまうもんだ」と言うと、軍務についていた時に「中国でスパイを始末したことがある」という告白を始めた。「隊長命令やけん、しょうがなかった。中年の中国人やった。……助けてくれ助けてくれいうて拝むとを、もういいからあっちへ行けっていうと、よろこんで逃げにかかったたい。それを、うしろから撃った。瞬間的に振り向いて、おればぐっとにらんだが、あのときの形相はいまでも思い出すことがあるほどだ。――戦争とは、そげなもんたい」。
和吉はその後ギャンブルにはまり借金まみれになり、ついに我慢の限界に達した留意子は離婚を決意する。一人暮らしを始めた和吉は心臓発作で死亡するが、発見されたのは二日たってからのことだった。和吉が胸のポケットに大切そうにしまっていたのは留意子が書いた事務的な手紙だった。和吉が頼れるのは留意子だけだったのだが、その留意子をとことんまで苦しめたあげく、このような最後を迎えた。和吉はギャンブルさえしなければ本当にいい人だったとふり返られるが、戦後に病的なほどギャンブルにのめり込んでいったのは、戦争体験がそうさせたのかもしれない。留意子は「これはある意味で和吉の自殺であったのかもしれない」と思った。
また真子も戦後波乱の歩みを始めることになる。新聞記者と結婚していたが、夫と子どもを置いて年下の人形師のもとに出奔したのである。周囲からは母親の「血」について噂されることとなる。留意子もそのわがままな振舞いにあきれ、同情的ではなかった。著者は気が進まないながらも1981年にこの人形師の藤本豊(これは仮名にしてある)に取材を行う。気が進まなかったのは藤本の評判がすこぶる悪かったからだ。夫婦は貧乏にまみれるばかりか、新しい夫は別に女を作ってもいた。真子はそのことに気づき、自殺未遂を繰り返すようになるなど奇妙ともいえる生活を始めたが、持病であった心臓が限界に達し51歳で死去する。藤本の経済力の無さと不品行の影響を疑わずにはいられない。
しかし著者が実際に会い、その周辺を調べると意外な事実がわかってくる。藤本は苦しい生活の中アナキズムの小新聞を発行していた。そもそも真子がこの人物と知り合ったのは、藤本の師匠の副島辰巳が店にアナキズムのシンボルである黒旗を翻えさせるような名物アナキストであったためだった。また留意子は後にここで働きはじめ、自立をしていくことにもなる。
この藤本の父もまたアナキストであった。逮捕され、官憲に追われ続けるという生活が父の寿命を縮めたのかもしれないと考え、アナキズムに対して複雑な思いを抱え続けることになる。
藤本は戦後に再び真子にアナキストやマスコミが注目を始めたことが彼女の最初の結婚生活を破壊したと考えていた。真子は平凡な主婦の座におさまっていたのに、大杉の娘ということで再び脚光を浴びてしまった。そればかりか、一部のアナキストたちは、真子に「ちゃんとしたアナキスト」と再婚させようという画策すらしていた、としている。
「わたしと出会ったとき、彼女はこういいましたよ。これまで自分の心の扉を開いてくれる者が誰もいなかったと。わたしが同類だということを直感して、やっと心を開く気になったんです。いわばわたしたちは、同じ傷をなめ合おうとしたといっていいでしょうな。口幅ったいいい方ですが、わたしは真子を世間の身勝手な脚光から引き戻してやりたいと思ったんです。その結果、ずいぶんひどいことを書かれたりはしましたけどね……」。
この話には藤本も知らない因縁がさらにあった。村上信彦の「大杉魔子の思いで」によると、当時中学四年だった村上が若い同志と労働運動社を訪ねると、オカッパ頭をしたまだ少女の可愛らしい真子がいた。村上は同志にこんなことを言う。「どうだい、僕ら三人のうちで、だれか将来、彼女と結婚したらすばらしくないか。大杉と野枝の子だよ。きっといい資質をもっているよ。僕はあの子を平凡な男と結婚させたくないな。もったいないものね」。
もちろん本気ではなく、ほんの軽口であったのだろう。しかしこの同志の中に、なんと藤本の父がいたのである。まだ生まれていない息子が将来この真子と結婚することになるなど、想像だにしなかっただろう。藤本が13歳の時に父は亡くなっているので、自分が真子の義理の父になったことは当然ながら知らないのだが、藤本自身も村上のこの文章を読んでいなかったため、奇縁としかいいようのない運命を知らなかったのであった。
さて、本書のタイトルは『ルイズ』になっている。ルイズから留意子となったが、再び「ルイズ」という名前を獲得していく物語でもある。
学生時代の修学旅行で東京に行った際、留意子は初めて異父兄の、のちに画家となる辻まことに会う。写真でしか見たことのない兄を見つけられるかと不安だったが、ホームに降り立つとすぐにその存在に気づき、「にいさん」「留意子」と、「人込みの中を吸い寄せられるように、二人は駆け寄り、手を取り合った」という。その光景は級友たちの話題となった。
食堂に入ると何が食べたいかと訊かれたので、とっさに「うちゃあ、ライスカレーが食べたかと」と答えると、まことは大笑いした。前年に会った姉の笑子も同じ答えをしたのだという。まことは「留意ちゃんはママのことは何かおぼえてるかい」と訊いた。「まことの口から聞くママという響きには、甘い懐かしさが感じられて、留意子の気持ちは和んだ。世の中には、こんなにも優しい男性がいるのかという印象を、まことに対して抱いた」。
しかし留意子が宿に帰って新聞を開くと、おそろしい記事を目にする。それはまことの父(つまり野枝の前夫)の辻潤が、「背広下駄ばきの異様な風態」で徘徊しているところを検束され、精神病院に収容されたというものだった。「兄もいまこの記事を読んでいるだろう」かということを考えたが、「兄はすでにこのことを知っていたに違いないと思えた」。大杉についてはいろいろと楽しい思い出を話してくれたのに、辻潤のことは一度も口にしなかったことを思い出したのであった。
この出来事も留意子にその生まれというものを意識させざるをえない出来事だったのだろうが、この修学旅行でもう一人会わなければならない人物がいた。大杉のかつての同志近藤憲二である。近藤は自身の生活も苦しい中、笑子や留意子に学資を送り続けていた。当然お礼を言わねばならぬのであるが、少女にとっては42歳のほとんど記憶にない恩人に会うのは気詰まりな出来事でもあっただろう。緊張しながら家を訪ねると、玄関に出てきた男が「やあ、ルイズがきた」と大声で言った。この男は服部浜二という大杉の同志で、留意子が来ると知って待っていたのだった。つづいて近藤が奥から出てきた。「近藤と服部からルイズ、ルイズと呼びかけられて、留意子は戸惑った。この十余年間、誰からも呼ばれることのなかった名である。なんともいえない戸惑いとともに、心のどこかに幼い日に還ったような幼いまでの懐かしさも湧いていた」。
二人は思い出話に花を咲かせ、「二人が生きていたらなあ……」と服部が呟いたときに、二人の眼には涙が光っていたのに留意子は気づいた。
藤本は真子は自分で「魔子」と書くことはなかったとふり返っている。子ども時代は大杉と伊藤の娘であることを受け入れていたかのような真子だが、その重みに耐えることはできなかった。あるいは、なまじ両親の(そして同志たちの)記憶があるだけに、年月を重ねるごとに受け入れがたいものに思えていったのかもしれない。一方の留意子は、この時に自分が「ルイズ」であると、そのことを受け入れることは、ほとんど記憶にない両親を心に刻むことだという意識がここで芽生えたのかもしれない。しかしそれを行動に移すのはまだまだ先のことである。
1953年、息子が小学校に入学すると、PTA委員となった留意子は学校新聞に寄稿する際に「王丸ルイ」と署名することに決めた。「何も知らず、何も学ばずに時勢にながされた戦時中の自分を省みるとき、留意子からルイに変わることで新しい出発としたかった。さすがに、父の命名してくれたルイズという名に戻すだけの勇気はなくて、それに一番近い名として選んだのがルイである」。
ルイは父の著作を買い求め、また市民学校などで勉強を始めた。公民館運営委員に推されたが「親の思想が悪いので」という理由で拒否され、翌年には今度は「本人の思想が悪いので」と拒まれた。「私って買いかぶられ過ぎてるのね」とルイは笑った。その頃、ルイが働いていた人形店主副島辰巳が亡くなった。副島はルイを雇うばかりでなく、不義理を働いた藤本にも仕事を与え、真子の面倒も何かと見ていた。副島は「私は副島辰巳以外の何者でもない」という短い言葉を書き残した。「一切の権威を認めず、個人の絶対的自由を希求し」たアナキストの棺は、黒旗でおおわれた。
夫はギャンブルにますますのめりこみ、ついにルイは離婚を決意する。「ともすればくじけそうになる自分の決意を貫くために」、ルイは『憲法の構成原理』という難解な法学書を書き写すことを始める。ルイは自分の戸籍を見て、そこに「国家の厳たる秩序を目的とする法律の意思を見た。そういう法律を、大杉も野枝もその他のアナキズムの徒はすべて否定して生きようとあらがったのだ。ルイは、大杉たちが否定した法律というものを、もっとよく知りたいと思い始めている」。そして一冊目の大学ノートを書き終えたとき、その表紙に「王丸ルイ」ではなく、「LOUISE」とのみ記したのであった。
「朝ドラ」的のようにも見えると書いてしまったが、それを遥かにしのぐ凄まじい生涯を真子もルイズも送ったものである。また次女の方の「エマ」こと幸子も、自分の写真が大杉の著作に使われているのを不審に思い実の両親が誰なのかを知るなど、これもかなりの出来事だろう。ルイは幸子と共に自分の生まれた場所を訪れたように、離れて育ったとはいえ関係は良好のようだ。また本書では脇役的であまり語られない笑子にも、かなりのドラマはあったことだろう。
大杉と伊藤の遺児たちの辿った道は、もちろん当時の日本の平均的なそれとは相当に異なるものだろう。しかしそれだからこそ日本の姿がかえってあぶりだされるということもあろうし、日本近現代史をこういった人々の視点から捉えるという作業は貴重なものであるし、語弊のある言い方を恐れずにいうと、ものすごく「面白い」ものでもある。
本書の単行本は1982年に刊行されている。存在は知っていたけれどなんとなく読んでいなかったのだが、『
伊藤野枝と代準介』をたまたま目にしてこちらもということで手にしてみた。一部両者の記述が食違っているところもあるが、このあたりのことは詳しくないもので比較評価をすることはできない。