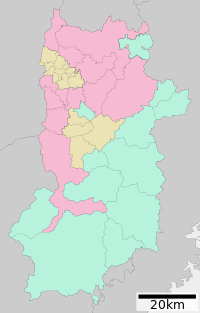[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(以下引用)
○高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)。高御産巣日神は、書紀に高皇産霊尊、「皇産霊此云2美武須毘1(皇産霊をみむすびと言う)」とあり、「古語拾遺」に「古語多加美武須比(たかみむすび)」、新撰姓氏録に「高彌牟須比命」とあるので読みが分かる。【「たかんすび」などと読むのは、音便に崩れた後世の読みである。】この名の意味は、「高」は美称、別名でも「高木(たかぎ)の神」と言う。【後に見える。】「御」も美称である。神産巣日神は、書紀には神皇産霊(かむみむすび)尊とあり、「皇」の字が一言多い。実際、高御産巣日神と双神であれば、この神も神御産巣日神とあって然るべきである。だが延喜式の出雲国造の神賀詞にも「高御魂(たかみむすび)、神魂(かみむすび)命」、新年祭の詞にも「神魂、高御魂」、また御巫の祭る神八座の中にも神産日神、高御産日尊【三代実録二巻に出たのもこれと同じ。】があり、これら二神を並べた中に、いずれも神産巣日神には「御」の字がない。新撰姓氏録にはたくさんの箇所にこの神の名があり、神御魂と書いた箇所もあるが、多くは「神魂」である。古言では同じ音が重なったとき、縮めて一音に言う例が少なくないので、【「倭迹々日(ヤマトととび)」という皇女の名を、「夜麻登々(やまとと)」としたり、旅人を「たびと」とするたぐいである。】これも「かみみ」と「み」が重なるので、多くの場合は縮めて言うのである。であれば、「かみ」の「み」に「御」の意味が含まれているのだ。神の字は「かみ」と読むべきである。【「かみみ」を縮めても、「かむみ」を縮めても、同じく「かみ」になるからである。「かむ」と読んだのでは、「御」の意味が備わらない。ただし書紀のように「神皇」とある場合は、「神」は「かむ」と読む。また「神皇」、「神御」共に、二文字で「かみ」と読んでもいいだろう。】
この名の意味は、「神御」は「高御」と同じく美称、「産巣日」は、字はすべて借字で、「産巣」は「生(むす)」である。それは息子、娘、また「苔むす」【万葉には「草武佐受(くさむさず)」もある。】などに言う「むす」で、ものが成り出ずるのを言う。【とすると、「産」の字は正字と考えても良い。書紀にも「産霊」とあり、「産日」と書かれることも多い。「む」の意味にこの字を書くのは、「生む」の意味である。仁徳天皇の歌で、「子生む」を「こむ」と言った例がある。だが「産巣(むす)」を「生む」の意でなく、「産」を「生む」の意とし、「巣日(すび)」を続けて考えても良さそうに思えるふしもある。その考えは七之巻五十七葉に出した。】「日」は書紀に「霊」とあるが、意味はよく当たっている。すべて物事の霊異(くしび)なのを「ひ」を言う。【「久志毘(くしび)」の「毘」も同じである。】高天の原にいませる天照大御神を地上から見上げて「日」と言うのも、天地に比類なく、最も霊異だからだ。比古(ひこ)、比賣(ひめ)などの「比」も、霊異であることの美称である。また禍津日、直毘などの「毘」もこれである。であるから、「産霊」は万物を生成する霊異(くしび)なる神霊(みたま)を言う。【以前、この「毘」は神佐備(かむさび)、荒備(あらび)などの「び」と同じで、「~ぶる」とも活用し、「~めく」という語に似ている。だから「むすび」とは生み出そうとしている状態を言うのかと考えていたが、それは誤っていた。「~ぶる」と活用する「び」ではない。だからあの「び」は常に「備」を書き、「むすび」は常に「毘」を書く。】この他にも、火産霊(ほむすび)、和久産巣日(わくむすび)、玉留産日(たまつめむすび)、生産日(いくむすび)、足産日(たるむすび)、角凝魂(つぬこりむすび)などの名がある。「むすび」の意味はみな同じである。世の中にありとあらゆることは、天地をはじめ、万物も事業も、この二柱の産巣日大神の産霊によって成り出ずるのである。
「神武東征」も、実は戦の結果ではなく単に大和に後から来た部族が成り上がっただけかもしれない。先住豪族(ニギハヤヒ系部族)が物部氏や大伴氏で、蘇我氏が天皇家の前代、ということだ。蘇我氏が天皇家以前の中心的豪族で「大王」だった可能性はあるだろう。確か、「天皇」と名乗るのは天武以後だった気がする。ついでだが、「日本」という国名も天武以降だったはずだ。
(以下引用)赤字部分は当ブログ(四月の雨)筆者による強調。
この文章は、安本美典氏の論考に触発されて少し調べてみた結果を述べるものである。そのため、氏の論に多くを負っている。すべてに賛成というわけではないのだが、面白い着眼点だと思っている。
なぜ神武天皇陵は所在不明になったのか?最近の歴史学では、第十代崇神天皇以後は実在したかも知れないが、それより前の九代の天皇はすべて架空の人物というのが通説とされている。それによれば、もともと存在しない天皇だから、陵墓もなくて当たり前なわけだ。
この件はすでに別の項で述べたので、ここでは繰り返さない。ただ私は古代天皇実在説に立って、改めて日本古代史を問い直してみたい。初期天皇架空説を唱える人でも、日本書紀に記載された地名を取り上げて、比定地を探っているらしいからだ。
神武天皇陵は実際には現在公式に認められているミサンザイでなく、その南方にある丸山古墳だという説があるそうだ。神武天皇架空説を採る人はにやにやするだけだろうが、実在説を採る人も「あんな小さな古墳が偉大な天皇家開闢の祖、神武天皇陵であるはずがない」と思うらしい。しかし神武天皇が当時はまだ一地方氏族で、物部氏の容認でやっと大和に住むことを許されただけだったら、大きな古墳を作らなかったのも当然だ。
別の項で、神武天皇を初代とする初期天皇家は、後代には賤業とされた職業に携わっていた可能性があることを述べた。つまり朱の採掘や、水銀の精錬である。はじめは賤業でも、財を蓄えて力を着ければ豪族になり、やがては王にもなる。神武が大和入りしてすぐ大王になり、初代天皇になったと考えるのは(日本書紀にそう書いてあるのだが)、誤りだろう。
神武から数代の天皇家は、まだどちらかと言えば貧しく暮らしていたのではないだろうか。丹敷では船が難破し、一行はほとんど潰滅状態に至っているのだ。大王になるどころか、生き延びるのが精一杯だっただろう。神武は、後代になって「祖業」を築いた偉大な先祖と見られたにしても、まだ成功を収めるに至らないまま早死にしたと思うのである。
よく考えてみると、神武から開化までの九代の天皇の陵墓には、あまり目立ったものがない。崇神に至って初めて、箸墓古墳のような大型古墳が現れる。それに神武天皇の出身地とされる宮崎(日向)には、あまり古い古墳はない。大和で大型古墳を作り始めたのが先であり、日向ではそれより遅れて始まったらしい。つまりもともと天皇家の祖先には、巨大墳墓を築造する伝統がなかったのではないだろうか。古墳の多くは、いわゆる地方豪族による築造である。「古墳時代」と言えば、「天皇を中心とした巨大陵墓」が次々と作られた時代、という認識を持つのだが、事実はそうではない。大和平野の古墳群には、天皇家と無関係な当時の豪族の墓が相当数含まれているだろう。
神武天皇陵がミサンザイに治定されたいきさつは、安本美典氏の著作に詳しい。大筋を言うと、幕末に尊皇思想が有力になってきたので、徳川幕府でも天皇陵の調査を行うことになり、宇都宮藩が主体となって各地の御陵を調査した。当時丸山古墳説とミサンザイ説があり、調査委員は丸山古墳が単なる小高い丘でとても古墳のようには見えないし、周囲に被差別民の部落があり、「薄汚い連中」の住むところで、神聖なる初代天皇の墳墓ではあり得ないと報告した、というのである。
ちなみに、幕末には財政が逼迫していたのだが、この修陵事業には相当な大金を出したらしい。幕府内でも天皇を神聖視する考え方はかなり浸透していたのだろう。宇都宮藩は水戸にも近く、尊皇の気風は強かったと考えられる。
また、当時は孝明天皇による陵墓参りが企画されており、被差別民を立ち退かせる必要があったのだが、日程的に間に合わないという判断があったとも言う。
この部落を洞(ほら)部落と呼んだそうだが、この名称にも何やら謎めいた感じがある。「洞」というのは、中国では少数民族の居住地域を指し、朝鮮では神などの住まう場所を指すことが多いようなのである。
神武天皇の崩御の後、その墓守として、九州から東征に同行した家人を付けたという伝承があるそうだ。その時点では賎民ではなかったらしい。むしろ由緒正しい家系として誇りを持っていただろう。
ところが律令制が始まった頃、天皇陵の墓守は「陵戸」とか「守戸」と呼ぶ賎民とされた。ただし朝廷から相応の土地や毎年の俸給を得ていたらしいので、案外過酷な身分ではなかったようだ。他の身分との通婚禁止という制約はあったが、これも一種の身分保護だった可能性がある。いずれにしても、幕末の時点で国家の庇護もなく、ひどい状態に置かれていたのは、どこかの時点で政府の方針が変化したのであろう。
私は、陵戸や守戸という「賎民」は良民より劣った身分と認識されたというより、本来は「聖別」された人々だったのだろうと思う。通婚禁止というのも、聖別された人と世俗の民の血が入り交じるのを怖れたのだろう。それがいつしか聖なる身分であることが忘れられ、タブーの面だけが残って「穢れ」と感じられるようになった。
彼らは死者を保護する人々である。古代には、さして穢れの意味はなかったらしい。だが時代が下るにつれ、死の世界を畏れ忌避する風潮が強まった。日本の土着の宗教には、天国と地獄の観念がない。生者の世界と死者の世界の二つしかないのである。生者の世界は明るい光に満ち、美と希望と快楽がある。しかし死者の世界には腐敗と汚穢だけがある。
強いて言えば、その境界は顕宗天皇による雄略天皇陵毀損記事である。兄(後の仁賢天皇)が驚いて弟を諫め、結局企てを取り止めた(古事記では、兄がほんの少し陵墓の土を掘ったという)のだが、天皇がいくら恨みを抱いたとは言え、陵墓に触るというのは、やはりタブーだったのだ。彼ら兄弟が雄略に殺された父の骨を掘り出させて直に見たというのも、珍しい話である。
人類の歴史における最初の神は、祖先神だっただろう。つまり自分の親や祖父などを祭り、かつて自分を育ててくれた頃と同じように死後も見守って欲しいと願うのである。ここでは死霊は本来守護の霊である。しかし戦いで殺し合ったりするうち、死者の怨念や呪いが残留する可能性も増しただろう。ただし、多くの民族では、死者をいかに安らかに眠らせるかに心を砕いたようであり、おそらく死に臨んだときの苦しみ(ほとんどの死は苦しみを伴う)から、多くの人が死に対する恐怖を抱いたに違いない。
古い形が残る地方の葬送儀礼を見ると、死者がこの世に帰ってくることのないように、二重三重にあの世に送る仕掛けになっているらしい。死者に送る別離の言葉にも、繰り返し「戻ってくるなよ」という言葉が現れる。愛する人であっても、幽霊は怖ろしいというわけだ。
死者を保護する人々としての聖別された人々は、こうした恐怖の世界の入り口に立ち、生者の世界との境界線上で仲立ちとなっているのである。死者を聖視する観念が薄れ、単なる古霊になったとき、そこにはタタリへの畏れだけが残った。だがその幽冥の境界で怖れ気もなく死者に触れる人々は、多くの人にとって怖ろしい世界に半身を浸している人々である。
この身分規定は、しかし、中世には一度完全に崩れたという。古くは技術的な職能人の多くが賎民の扱いをされたらしいが、技術革新が相次ぐ中で、維持できなくなったのだろう。江戸時代にも職能人、芸能人で賎民身分を脱する人々がいた。
それに比較して、洞部落の人々はまるで朝廷からうち捨てられたかのような暮らしをしていた。私はここに何か歴史的ないきさつがあったのではないかという感じがするのである。
それは神武天皇系と違った皇統があり、その系統が長く天皇家を継いだため、神武の祭祀がいつか忘れられ、途絶えてしまったのではないかという仮説である。
神武天皇を実在した人物と考えるならば、少なくとも天武天皇の頃にはまだ陵墓のある場所は判明していた。天武天皇は壬申の乱の際、高市縣主の許梅(コメ)なる人物が事代主神の託宣を告げたのを受けて、許梅を遣わして神武天皇陵を祭り拝ませたという。
この頃には、天皇が陵墓に直接出かけて拝むことはなかったようである。死の穢れを怖れたのだろう。だが古くは、それほど強いタブーとは思われていなかったようである。仁徳紀の白鳥陵の陵守を役丁(えよぼろ)に充てようとして起こった怪異、顕宗紀の雄略天皇陵毀損事件などは、いわゆる「触穢(しょくえ)」に当たるだろう。神功紀の「阿豆那比(あずない)の罪」の記事も、天皇自ら遺骸を確認したのかもしれない。
天武天皇は、また天照大神を尊崇した天皇でもあった。われわれは天照大神こそ天皇家の祖先神であり、最高神であるという「常識」を持っているので何ら疑問を抱かないが、そのつもりで読むと、実は崇神以来、天智にいたる天皇家では、三輪の大神である大物主神の方がどちらかと言えば有力だったのだ。
崇神天皇紀の五年から六年にかけて、疫病の流行や百姓の流離、時には一揆も起こったので、内殿に並べて祭ってあった天照大神と倭大国魂神をいずれも外に出したという記事がある。それまでこの二柱の神と天皇が同殿共床していたのである。それがあまりにも畏れ多く、祟ったのだと考えたわけだ。その後天照大神は各地を巡幸することになる。
倭大国魂神は、それまで登場しない名前だが、大物主神と同神である。宮中から出すといっても、元々三輪山の大神だったから、宮中の神は分霊、分祀である。つまり宮中の祭祀をやめただけなのだが、それではあまりにも失礼だというので、この分霊にも新たな名を与えて別に祭ったのだろう。崇神紀には明示しないが、垂仁紀では穴磯邑(あなしのむら)に祭ったと書いてある。
大物主神と同神だというのは、この前後の記事で倭大国魂神は何も言っていないが、大物主神は「私を大田田根子に祭らせよ」など、あれこれ言っていて、事件(タタリ)の主体になっているからである。なお古事記では倭大国魂神の名は出て来ない。すべて大物主神のことである。
崇神紀と垂仁紀細註はこの記事が重複しているのだが、細かく見るとずいぶん違う。すでに倭姫によって天照大神が伊勢にたどり着いた後、倭大国魂神が神託を下したとある。崇神紀では崩御の年を120才と書いてあるのに、神託では、崇神が長生きできなかったとあるなど、かなり怪しげである。
いずれにせよ崇神八年には、天皇は大物主神を讃えて大々的な祭を行っているが、天照大神は豊鍬入姫に託し、その後各地をさすらうに任せた。
(以下引用)
。○正勝云々。正勝は、書紀に「正哉」と書いてあるのに合わせ、これも書紀も「まさか」と読む。「哉(かな)」を「か」と読むのは、論じるまでもない。【書紀の注釈書で「まさや」と読んだのは間違いである。】「勝」を「か」と読むのは、この記に「正鹿山津見(まさかやまつみ)」とある神を、書紀では「正勝山祇」と書いてある。これも両者共に「か」と読むべきである。【書紀の訓注には「正勝、これを『まさかつ』と読む」とあるが、大江家の伝本には最後の『つ』がないという。その本がいいだろう。】ここも同じだ。言葉の意味は、書紀の文字の通りで、「本当か」と驚いている様子である。【この記では、やはり字の通り、「正しく勝ったぞ」と誇っているようにも取れる。そうであれば「まさかつ」と読むべきである。しかし書紀と考え合わせると、やはり上述の解釈が良い。】吾勝は、後の文に「自ら『私の勝ちだ』と言って」とある意味だ。書紀の一書に「男の神を生んだので、直ちに言挙げして、『まさにか、私の勝ちだ』と言った。そこでそれを神の名とした」とある。勝速日は「かちはやび」と読む。【古来「かつのはやひ」と読んでいるのは、古言の様式を知らないからである。】後の文に「勝佐備(かちさび)に」とあるのと同じ意で、【「佐備」について、そこで述べることを考え合わせよ。】速(はや)は疾く、激しく、猛々しいという意味、日(び)は「ぶる」とも活用し、その状態を言う辞なので、速日とはつまり「ちはやぶる」の「はやぶる」と同じ言葉である。既に出た甕速日、樋速日、また饒速日などとも同じ。【日の字にこだわって言う説などは、例の古言を知らぬこじつけだ。】忍穗耳は、大耳(おおしみみ)で、美称である。忍(おし)が「大し」であることは、既に忍許呂別(おしころわけ)のところ【伝五の八葉】で述べた。穂も「大(おお:旧仮名おほ)」である。「おほ」の「お」を省いて「ほ」とのみ書いた例は多い。特に書紀では三穂之碕とある地名を、この記では御大之前と書いてあるのは、ここによく合っている。【邇々藝(ににぎ)命から三代の名は、みな稲穂に関わる言葉で称えており、その例として、これも字の通り稲穂の意味に取れなくもないが、かの三代は天降って後、この水穂の国を治めたことから、稲穂をもって称え名としたのだが、この神は地上の国には降らなかったので、意味が違う。書紀にある齋庭(ゆにわ)の詔(第九段一書第二)も、邇々藝命の段に係わっているのを考えても分かる。続く三代の名については、それぞれそのところで言う。】耳は尊称である。【耳はもちろん借字である。】後の文に「布帝耳(ふてみみ)神の名がある。神武天皇の子に「何々耳」の名が多く、その他にも人名に多いのは、みな尊称である。書紀の一書に「忍穂根(おしほね)尊」【「忍骨」とも書く。】という名があるが、「穂」は上記と同様、「根」はやはり尊称で、「何々根」という名も非常に多い。前述の「阿夜訶志古泥(あやかしこね)神のところ【伝三の四十五葉】で述べた。次の日子根の「根」も同じ。ところで伊邪河の宮(開化天皇)の段にある神大根(かむおおね)王【開化天皇の孫。】は、書紀では「神骨」とある。この例からも、忍穗根は忍大根であることが分かり、また「穂耳」は「大耳」であることがますます明らかだ。さらに言うと、書紀神代の下巻には、「勝速日尊兒大耳尊」とあるので、納得できるだろう。【これは「忍」という語を省いて、天忍穂耳命と言おうとするのである。「尊兒(みことご)」は、尊びかつ親しんで言う語である。「みことのこ」と言うのではない。およそこの神の名については、従来の説はすべて誤っている。他の例をよく考え合わせて、いにしえの心と言葉を尋ね求めるべきだ。】耳という尊称の意味は、「み」は「ひ」に通い、あの産霊の神の「霊(ひ)」であるが、【産霊の意味は、伝三の十三葉で言った。】それを「霊々(ひひ)」と重ねたのである。開化天皇の名の大毘々(おおびび)命というのがそうだ。これを書紀では太日々(ふとびび)尊とあり、垂仁の巻には太耳という人物も登場するので、「日々」と「耳」は同じだと分かる。また明の宮(應神天皇)の段の前津見(まえつみ)という人物を、書紀では前津耳と書いてある【その他、水垣の宮(崇神天皇)の段の陶津耳という人の名が、旧事紀では「大陶祇(おおすえつみ)」としているのも、何か根拠があってのことだろう。】ので、「耳」というのは「み」を二つ重ねた名で、「見」はその一つを省いたものだと知るべきである。神名や人名に「何々見」というのが多いのは、みなこれであって、水垣の宮の段の岐比佐都美(きいさつみ)、書紀の武茅渟祇(たけちぬつみ)などの「つみ」も「つみみ」の略だ。【これに倣うと、山津見、綿津見、大加牟豆美なども、同じく「つみみ」ではあるまいか。また月夜見の見も耳ではないだろうか。】ここで、耳と日々が通うことからすると、「つみ」はまた「つび」と通い、禍津日の神、庭高津日神などの名によって知られる。それに「何々須美」という名と、「何々須毘」という名とが通うことは、次に見える。そうした例から、耳は「霊霊(ひひ)」の意味であることを理解すべきである。ところで、山城国風土記に、宇治郡木幡社の名は天忍穂根尊、【延喜式神名帳に、同郡の許波多(こばた)神社が載っている。】また延喜式では、豊前国田川郡に忍骨神社、【続日本後紀六に、この社の山のことが出ている。】土左国香美郡に天忍穂別神社、【別(わけ)も耳、根と同様の尊称である。】などがある。伊勢の外宮には、忍穂井という井戸もある。○これ以下の神については、いずれも「八尺勾ソウ(王+總のつくり)之云々」、「奴那登母云々」という文がないのは、上述したことに譲って、省いたのである。○天之菩卑能命(あめのほひのみこと)。【「能」の字を添えたのは珍しい。】これも元は上述の「穂耳」と同じで、「菩(ほ)」は「大(おほ)」である。卑(ひ)は「み」と通い、それは上述の「耳」の意味である。このように菩卑(ほひ)も穂耳と同じであるなら、吾勝命と兄弟の名が同じになるが、なぜかというと、上述の三女神のうち、多紀理と多岐都が同じであったように、また書紀では次の熊野久須毘命も忍蹈(おしほみ)命とあって、忍穂耳と全く同じであるように、これらの兄弟の名は、わずかな違いで分けただけなのである。【延喜六年の日本紀竟宴で、天穂日命を歌った矢田部公望、「阿麿能褒臂、俄彌農美飫野簸、耶佐賀珥廼、伊朋津儒波屡濃、儔莽登胡楚耆鶏(あまのほひ、かみのみおやは、やさかにの、いおつすばるの、たまとこそきけ)」】神名帳には、山城国宇治郡、因幡国高草郡、出雲国能義郡などに、天穂日神社がある。出雲国風土記に天之夫比(あめのふひ)命とあるのも、この神であろう。
(以下引用)
箸墓古墳
| この項目に含まれる文字「箸」は、オペレーティングシステムやブラウザなどの環境により表示が異なります。 |
| 箸墓古墳 | |
|---|---|
 墳丘全景(右に前方部、左に後円部) |
|
| 別名 | 箸中山古墳 |
| 所属 | 纒向古墳群 |
| 所在地 | 奈良県桜井市箸中 |
| 位置 | 北緯34度32分21.34秒 東経135度50分28.42秒座標: 北緯34度32分21.34秒 東経135度50分28.42秒 |
| 形状 | 前方後円墳 |
| 規模 | 墳丘長278m 高さ30m |
| 出土品 | 特殊器台形埴輪・壷形埴輪 |
| 築造時期 | 3世紀後半 |
| 被葬者 | (宮内庁治定)倭迹迹日百襲姫命 (笠井新也ほか)卑弥呼 |
| 陵墓 | 宮内庁治定「大市墓」 |
| 史跡 | 国の史跡「箸墓古墳周濠」 |
| 特記事項 | 全国第11位/奈良県第3位の規模[1] 全国最古級の前方後円墳 『日本書紀』崇神天皇紀に記述 |
| 地図 |

|
箸墓古墳(はしはかこふん)、箸中山古墳(はしなかやまこふん)は、奈良県桜井市箸中にある古墳。形状は前方後円墳。実際の被葬者は不明だが、宮内庁により「大市墓(おおいちのはか)」として第7代孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫命の墓に治定(じじょう)されている。また、笠井新也の研究以来、邪馬台国の女王卑弥呼の墓ではないかとする学説がある[2][3]。周濠部分は国の史跡に指定されているほか[4]、一部が「箸中大池」としてため池百選の1つにも選定されている[5]。百襲姫の陰部に箸が突き刺さり、絶命したことが名前の由来である[6]。
概要[編集]
奈良盆地東南部、三輪山北西山麓の扇状地帯に広がる大和・柳本古墳群に含まれる纒向古墳群(箸中古墳群)の盟主的古墳であり、纒向遺跡箸中地区に位置する。出現期古墳の中でも最古級と考えられている前方後円墳である。
築造年代は、墳丘周辺の周壕から出土した土器(土師器)の考古学的年代決定論と、土器に付着した炭化物による炭素14年代測定法により、邪馬台国の卑弥呼の没年(248年から遠くない頃)に近い3世紀中頃から後半とする説がある。一方で、近年炭素14年代測定法では、実年代より50-100年程度古く推定されることが明らかとなっていることや、古墳の規模および様式が魏志倭人伝の記述と異なっていることなどを理由に、4世紀中期以降とする説もある。 現在は宮内庁により陵墓として管理されており、研究者や国民の墳丘への自由な立ち入りが禁止されている。倭迹迹日百襲姫命とは、『日本書紀』では崇神天皇の祖父孝元天皇の姉妹である。大市は古墳のある地名。『古事記』では、夜麻登登母母曽毘売(やまととももそびめ)命である。
考古学の世界では、大正期から邪馬台国畿内説を唱えていた笠井新也により「女王卑弥呼=倭迹迹日百襲姫命」説が提唱され[7][8]、後に「箸墓古墳=卑弥呼の墓」説へと進展[2][3]、今日の議論にも繋がる先駆的研究となった[9]。
名の由来[編集]
名前の由来は、百襲姫の陰部に箸が突き刺さり絶命したという説話に基づく。『日本書紀』崇神天皇10年9月の条には、つぎのような説話が載せられている。一般に「三輪山伝説」と呼ばれている。
倭迹迹日百襲姫命 ()、大物主神 ()の妻と為る。然れども其の神常に昼は見えずして、夜のみ来 ()す。倭迹迹姫命は、夫に語りて曰く、「君常に昼は見えずして、夜のみ来す。分明に其の尊顔を視ること得ず。願わくば暫留まりたまへ。明旦に、仰ぎて美麗しき威儀 ()を勤 ()たてまつらむと欲ふ」といふ。大神対 ()へて曰 ()はく、「言理 ()灼然 ()なり、吾明旦に汝が櫛笥 ()に入りて居らむ。願はくば吾が形にな驚きましそ」とのたまふ。ここで、倭迹迹姫命は心の内で密かに怪しんだが、明くる朝を待って櫛笥 ()を見れば、まことに美麗な小蛇 ()がいた。その長さ太さは衣紐 ()ぐらいであった。それに驚いて叫んだ。大神は恥じて、人の形とになって、其の妻に謂りて曰はく「汝、忍びずして吾に羞 ()せつ。吾還りて汝に羞せむ」とのたまふ。よって大空をかけて、御諸山に登ってしまった。ここで倭迹迹姫命仰ぎ見て、悔いて座り込んでしまった。「則ち箸に陰 ()を憧 ()きて薨 ()りましぬ。乃ち大市に葬りまつる。故、時人、其の墓を号けて、箸墓と謂ふ。(所々現代語)
また、築造について『日本書紀』には、
「墓は昼は人が作り、夜は神が作った。(昼は)大坂山の石を運んでつくった。山から墓に至るまで人々が列をなして並び手渡しをして運んだ。時の人は歌った。大坂に 継ぎ登れる 石むらを 手ごしに越さば 越しかてむかも」
と記されている。
なお、箸が日本に伝来した時期(7世紀か)と神話における説話との間に大きなずれがあるところから、古墳を作成した集団である土師氏の墓、つまり土師墓から箸墓になったという土橋寛の説もある。
孝謙上皇との出会い・権力の拡大
この年孝謙上皇は、平城宮の改修などの関係で近江国の「保良宮」と呼ばれる場所に滞在しておられましたが、病気に倒れてしまい、その際に「禅師」として入り込んだ道鏡によって非常に熱心な看病が行われたとされています。
看病のおかげかどうか、孝謙上皇の病気は治り、その「ご恩」に心打たれた孝謙上皇は、それ以降道鏡と様々な意味で関係性を深め、実質的な「寵愛」・「政治的重用」を受けるようになります。
「謎の僧侶」を特別扱いし始めたことに周囲は不信感を抱き、当時の淳仁天皇は事あるごとにそれに対する「箴言(注意)」を行いますが、孝謙上皇は指摘されるとむしろ逆上して怒りを爆発させたようで、続日本紀に「高野天皇、帝と隙あり」と明記されたように、淳仁天皇と孝謙上皇の関係性は一気に悪化していくことになりました。
なお、上皇は批判を受けるほどに一層道鏡へ入れ込むことになったのか、762年には淳仁天皇を差し置いて自らが国家的な決定を担うと主張し、淳仁天皇は祭祀などの儀式を行う形式的な存在でよいとするなど、次第にその「暴走」傾向が顕著になっていきました。
権力基盤の確立・称徳天皇と道鏡の時代
当時の実質的な政治のトップであり、独自の権力基盤を持っていた「藤原仲麻呂」が、道鏡と孝謙上皇の関係が深まることに懸念を感じ、自ら兵を率いてクーデターを起こすことを計画します。
クーデターにあたっては、当初は軍事力を有することから優勢かと思われた仲麻呂ですが、密告などにより孝謙上皇側に先手を打たれ、吉備真備などの官軍が征伐に派遣されたこともあり、本人を含む一族の大半が戦死する完全な失敗という結果に終わりました。
この仲麻呂の乱の終結後は、これまで政治権力を振るってきた仲麻呂陣営が処罰を受け流罪などになった人物も多く、元より上皇と仲が悪かった淳仁天皇も「仲麻呂側」の人物として淡路島に送られて謎の死を遂げるなど、孝謙上皇は自らの反逆者と思われる存在を次々に「消して」いきます。
結果として、孝謙上皇は実質的に再び即位(称徳天皇)する形でトップへと返り咲き、今まで以上に道鏡を寵愛することが出来る環境を手に入れる形にもなりました。
ざっくり言えば、当時の朝廷では政治面での「称徳天皇(孝謙上皇)」と仏教面での「道鏡」の二頭体制の構図が確立された。と言ってもよいでしょう。また、道教の弟である「弓削浄人」も朝廷で地位を上げるなど、「道鏡陣営」とも言える政治基盤も整えられていくことになりました。
なお、この時代には僧侶である道鏡が権力者として君臨し、様々な乱世を経験した称徳天皇も仏教に入れ込んだことから、鎮護国家を願って「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとう・だらに)」を製作させたり、寺院の整備をより推進するなど、仏教色・仏教保護の色彩の強い政治が行われました。また、神社についても保護政策が展開されますが、仏を護る「護法善神」という形で「神仏習合」の形態を持つことが一層増えていきました。
「宇佐八幡宮神事件」による失脚
孝謙上皇(称徳天皇)からの寵愛によって時の権力者に上り詰めた道鏡ですが、その権力の失墜・失脚はあっけなく訪れます。
当時の構図としては、独身で皇子などもおらず、その上称徳天皇の意向で皇太子が決定されていない中、天皇が高齢になる中で次の天皇が誰になるのか。という宮中・朝廷の不安と疑念が渦巻く状況でした。
そんな中、769年(神護景雲3年)5月に道鏡の弟であり九州防衛のトップ「太宰帥」であった弓削浄人が、突如大分の宇佐八幡宮(当時は皇室からの信仰が非常に強い神社でした)の「ご神託」として、「道鏡を皇位につければ世の中は平和になる」というメッセージを平城京に送ったこと(一般には偽のご神託であるともされます)で、状況は一変します。
道鏡を寵愛して来た称徳天皇は、その「ご神託」を確認しようということで、和気清麻呂を派遣しますが、持ち帰った答えは「皇位継承は皇族の人間にすべし」といった内容であり、称徳天皇は激怒して清麻呂に「別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)」という醜い名前を付けて流罪とします。
しかしながら、激怒した称徳天皇も結果としては無理に道鏡を皇位に就けようとはせずに、10月にはむやみに皇位を求めてはいけない・自らが後継者を決定するといった詔を発表して、状況を鎮静化しようとします。
天皇は、翌年770年(宝亀元年)に崩御し、どのような経緯で決定されたかは諸説ありますがその「遺言」として白壁王を光仁天皇として即位させることになり、道鏡が皇位に就くという流れは完全に排除されます。
唯一の後ろ盾と言っても良い称徳天皇を失った道鏡は、大きな処罰を受けることはなかったものの、現在の栃木県にあたる下野国の薬師寺別当に実質的な配流(流罪)となり、まもなく772年に亡くなりました。
道鏡の評価について
下世話なものも含む様々な「道鏡伝説」は、奈良時代からそのすべてが伝わっていたというよりは、どうやら後世になって様々な尾ひれがついて無限に拡大していった「人物像」である可能性が高いとも言えますが、「日本三大悪人」になぞらえる解釈や、道鏡を「奇怪な僧侶」としてロシアのラスプーチンになぞらえるインターネット上の解釈も複数見られるなど、現代に至るまで「悪いイメージ」がつきまとう存在であることは否定できません。
一方で、歴史的な解釈としては「本当に道鏡は悪人だったのか?」という疑問が呈されることも近年やや増えており、一部では再評価の兆しや、特に宇佐八幡宮事件などについては学問的に様々な解釈が見られることも確かです。
そもそも、経歴を追っていく中でも、道鏡が何かを自らで大規模に粛清したとか、特定の存在を極端に弾圧したとか、誰かと共謀してまれに見るような凶悪な働きを果たした。といったような歴史に残る「具体的な悪行」は特に伝わっていないことは紛れもない事実です。
そういった観点を考慮し、本記事では様々な「道鏡解説記事」にありがちなセンセーショナルなエピソードなどをなるべく退けて、一般的に伝わる氏の経歴のみを淡々と解説しています。