×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
井上やすし「キネマの天地」読了。良作。
演劇界、映画界の実態を喜劇的に描きながら、読後感が非常にいい。特に、美人女優の現実の悲惨さや汚さがよく分かる。しかし、それも「演劇の魔」に魅入られたことによる幸福な悲惨である。
「選ばれてあることの恍惚と不安 我にあり」
太宰治の或る作品の冒頭のエピグラフである。「選ばれてある」とは、「選ばれた者として存在する」ということ。
なお、言葉の使い方が面白い。「しょっちゅう」を「初中終」と書いて、「しょっちゅう」と振り仮名を付けたり、「つよい」を「強い」ではなく「勁い」という漢字を用いたりしている。
前者は、たしかに「初中(しょちゅう)」だけでは全体にはならないから「終」を入れることで完全になるし、また「終」の「しゅう」と「中」の「ちゅう」は音として融合するとすれば、「初中終」で意味も音も完全な「しょっちゅう」になる、と考えられる。実際に、「初中終」で「しょっちゅう」と読むというのが前例があるのか、夏目漱石的な当て字なのかは知らない。
後者は、私も「強い」と「勁い」から受ける感じが違うし、作中の使い方も確かに「勁い」がニュアンスとしていいと思う。要するに、「強い」はレスラー的、力士的なパワーの「強さ」であり、「勁い」は「毅然として、すっと立ち、外部の力によって倒れることのない」感じだ。首の立った感じ(「勁」は頸部の「頸」と似ている。)であり、「疾風に勁草を知る」の疾風を物ともせずに立ち続ける草の勁さだ。
演劇界、映画界の実態を喜劇的に描きながら、読後感が非常にいい。特に、美人女優の現実の悲惨さや汚さがよく分かる。しかし、それも「演劇の魔」に魅入られたことによる幸福な悲惨である。
「選ばれてあることの恍惚と不安 我にあり」
太宰治の或る作品の冒頭のエピグラフである。「選ばれてある」とは、「選ばれた者として存在する」ということ。
なお、言葉の使い方が面白い。「しょっちゅう」を「初中終」と書いて、「しょっちゅう」と振り仮名を付けたり、「つよい」を「強い」ではなく「勁い」という漢字を用いたりしている。
前者は、たしかに「初中(しょちゅう)」だけでは全体にはならないから「終」を入れることで完全になるし、また「終」の「しゅう」と「中」の「ちゅう」は音として融合するとすれば、「初中終」で意味も音も完全な「しょっちゅう」になる、と考えられる。実際に、「初中終」で「しょっちゅう」と読むというのが前例があるのか、夏目漱石的な当て字なのかは知らない。
後者は、私も「強い」と「勁い」から受ける感じが違うし、作中の使い方も確かに「勁い」がニュアンスとしていいと思う。要するに、「強い」はレスラー的、力士的なパワーの「強さ」であり、「勁い」は「毅然として、すっと立ち、外部の力によって倒れることのない」感じだ。首の立った感じ(「勁」は頸部の「頸」と似ている。)であり、「疾風に勁草を知る」の疾風を物ともせずに立ち続ける草の勁さだ。
PR
この写真で、封蝋の使い方が初めて理解できた。私は、単に封した紙(手紙)の上に封蝋をするのだと思っていて、それなら、剥がしてから封し直すこともできるのではないかと思っていた。
下のように、封した上から紐で縛り、その縛り目に封蝋をするのなら、紐を切るか封蝋を壊さないと手紙が読めないわけで、信書の秘密が守られるわけである。
下のように、封した上から紐で縛り、その縛り目に封蝋をするのなら、紐を切るか封蝋を壊さないと手紙が読めないわけで、信書の秘密が守られるわけである。
封蝋ってまだ売ってるのね。https://www.hankoya.com/shop/sealingstamp/ …
持明院統と大覚寺統という名前の由来は下の回答にある通りだろうが、その寺自体、現存していないだろうから、イメージが湧かない。後深草統、亀山統と呼ぶべきではないのか。なぜ、御所の名前を二つの皇統の名にする必要があるのか、理解できない。
暗記するなら「(南・)90・亀山・大覚寺」と、一方を中心に(強調して)覚えるといいかもしれない。「北・89・後深草・持明院」よりは語呂がいい。(下の記述の順序どおり、持明院統が北朝としての話である。)
(以下引用)
88代の後嵯峨天皇の子の89代後深草天皇(持明院統))と90代亀山天皇(大覚寺統)が退位後に御所とした寺院の名前に由来します。二つの皇統で後継者争いが起きて幕府の調停で交互に天皇を出すようになり、これが後に北朝と南朝に分裂します。
暗記するなら「(南・)90・亀山・大覚寺」と、一方を中心に(強調して)覚えるといいかもしれない。「北・89・後深草・持明院」よりは語呂がいい。(下の記述の順序どおり、持明院統が北朝としての話である。)
(以下引用)
88代の後嵯峨天皇の子の89代後深草天皇(持明院統))と90代亀山天皇(大覚寺統)が退位後に御所とした寺院の名前に由来します。二つの皇統で後継者争いが起きて幕府の調停で交互に天皇を出すようになり、これが後に北朝と南朝に分裂します。
私は、子供のころに「てりゅうだん」という読み方を聞いた時に、それは間違いだろう、と思ったのだが、旧日本陸軍や自衛隊ではそれが当たり前の読み方らしい。
なぜ「てりゅうだん」という読み方を奇異に感じるのかと言うと、「て」は訓読み、「りゅうだん」は音読みという湯桶読みで、そういう読み方の熟語は少ないからである。「湯桶(ゆとう)」にしても、本来は「ゆおけ」でいいはずだ。
ただ、専門家集団というのは一般社会とは違う「専門語」をわざわざ作る傾向があり、軍隊の独自用語もそれだろう。いわゆる「ジャーゴン」である。医療用語や科学用語、英文法用語などもジャーゴンだらけだ。要するに、素人の目に不可解なものにし、内部の汚い事実を隠し、外部には偉く見せるためである。
なお、「手榴弾」は「榴弾」が先に存在し、手で投げる榴弾だから「手投げの榴弾」ということで「て・りゅうだん」でいいのだ、という理屈は可能である。しかし、マスコミは文系秀才が多いから、その「湯桶読み」を奇異に感じ、「しゅりゅうだん」と呼んできたのだろう。
(ウィキペディアより転載)
なぜ「てりゅうだん」という読み方を奇異に感じるのかと言うと、「て」は訓読み、「りゅうだん」は音読みという湯桶読みで、そういう読み方の熟語は少ないからである。「湯桶(ゆとう)」にしても、本来は「ゆおけ」でいいはずだ。
ただ、専門家集団というのは一般社会とは違う「専門語」をわざわざ作る傾向があり、軍隊の独自用語もそれだろう。いわゆる「ジャーゴン」である。医療用語や科学用語、英文法用語などもジャーゴンだらけだ。要するに、素人の目に不可解なものにし、内部の汚い事実を隠し、外部には偉く見せるためである。
なお、「手榴弾」は「榴弾」が先に存在し、手で投げる榴弾だから「手投げの榴弾」ということで「て・りゅうだん」でいいのだ、という理屈は可能である。しかし、マスコミは文系秀才が多いから、その「湯桶読み」を奇異に感じ、「しゅりゅうだん」と呼んできたのだろう。
(ウィキペディアより転載)
日本での呼称[編集]
現在、日本では手榴弾をマスコミのみが「しゅりゅうだん」または「てなげだん」と呼称し、名称が統一されていないが、日本軍や自衛隊では手榴弾は一貫して「てりゅうだん」と呼称される。
短編漫画、あるいは映画脚本ネタ
大学生のサークル仲間が男女数人で旅行をする。
そのうちの一人が旅行の様子をずっとビデオ撮影している。
旅行最終日、宴会をする、その様子を撮影中に撮影者は酔っぱらってビデオを片隅に置いたまま寝室(他の部屋)に行って寝る。ところが、ビデオのスイッチを切り忘れ、ビデオは廻ったまま、部屋の様子が撮影され続ける。
後は、撮影されていることに気づかず、残った連中は、その場にいない人間の悪口で大盛り上がり、果てには、その場にいない人間の恋人(女)が、残っていた連中と大乱交。
(映画なら、途中途中で、ビデオの「銃口(カメラアイ)」の画像が挿入される。「2001年宇宙の旅」のハルがボウマン船長らの「悪だくみ」を「見ている」シーンのように。)
(追記)ちなみに、これです。
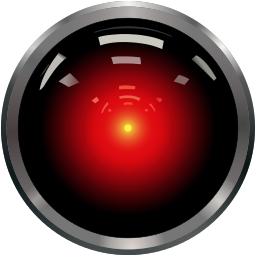
最後のシーンは、翌日になって、「撮影係」が宴会の場のビデオを見つけて、「まだ動いている。ちぇっつ、電池の無駄遣いしちゃったなあ」というシーンで終わるか、あるいは、その撮影内容を自分で見て顔を青ざめさせるシーンか、或いは後日、みんなで「旅行の思い出ビデオ」鑑賞会をしているシーンで終わってもいい。
なお、宴会の場で、先に酔いつぶれてその場で寝ていて、ふと目が覚めた時に「友人」による私への悪口を聞いたのは私自身の経験。起きるに起きられず弱ったが、自分の「友人」の本心、あるいはその正体を知ったのは衝撃だった。また、組織の上役であった時に、隣室に私がいることも知らず、部下のひとり(私にいつもおべっかを使う人間だった)が私の悪口を言っているのを聞いたこともある。まあ、考えれば、自分だって「表の顔」と「裏の顔」を持っているわけだが、なぜか他人(特に友人や部下)の「表の顔」をつい信じ込むのが人間の愚かしさなのだろう。
大学生のサークル仲間が男女数人で旅行をする。
そのうちの一人が旅行の様子をずっとビデオ撮影している。
旅行最終日、宴会をする、その様子を撮影中に撮影者は酔っぱらってビデオを片隅に置いたまま寝室(他の部屋)に行って寝る。ところが、ビデオのスイッチを切り忘れ、ビデオは廻ったまま、部屋の様子が撮影され続ける。
後は、撮影されていることに気づかず、残った連中は、その場にいない人間の悪口で大盛り上がり、果てには、その場にいない人間の恋人(女)が、残っていた連中と大乱交。
(映画なら、途中途中で、ビデオの「銃口(カメラアイ)」の画像が挿入される。「2001年宇宙の旅」のハルがボウマン船長らの「悪だくみ」を「見ている」シーンのように。)
(追記)ちなみに、これです。
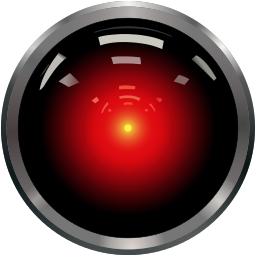
最後のシーンは、翌日になって、「撮影係」が宴会の場のビデオを見つけて、「まだ動いている。ちぇっつ、電池の無駄遣いしちゃったなあ」というシーンで終わるか、あるいは、その撮影内容を自分で見て顔を青ざめさせるシーンか、或いは後日、みんなで「旅行の思い出ビデオ」鑑賞会をしているシーンで終わってもいい。
なお、宴会の場で、先に酔いつぶれてその場で寝ていて、ふと目が覚めた時に「友人」による私への悪口を聞いたのは私自身の経験。起きるに起きられず弱ったが、自分の「友人」の本心、あるいはその正体を知ったのは衝撃だった。また、組織の上役であった時に、隣室に私がいることも知らず、部下のひとり(私にいつもおべっかを使う人間だった)が私の悪口を言っているのを聞いたこともある。まあ、考えれば、自分だって「表の顔」と「裏の顔」を持っているわけだが、なぜか他人(特に友人や部下)の「表の顔」をつい信じ込むのが人間の愚かしさなのだろう。
プロフィール
HN:
冬山想南
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
P R


