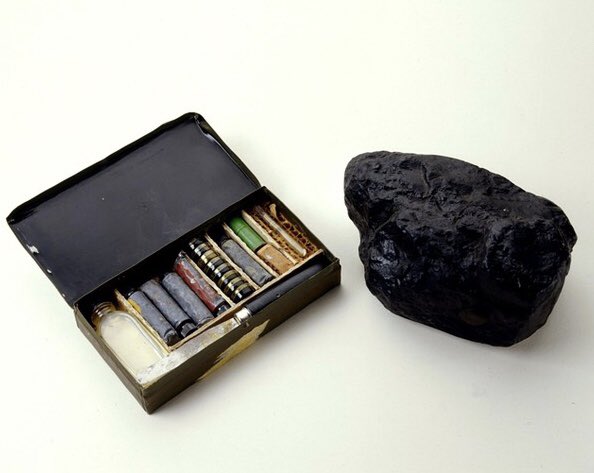2: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:23:18.52 ID:YHbYEey7d
この他にも、『もし神様が天地万物を造ったというなら、なぜ神様は悪も一緒に造ったのか?(神様がつくった世界に悪があるのは変じゃないのか?)』などと質問され答えに窮していたようです。
ザビエルは、1549年に日本に来て、2年後の1551年に帰国しますが、
日本を去った後、イエズス会の同僚との往復書簡の中で
「もう精根尽き果てた。自分の限界を試された。」と正直に告白しています。
集団原理の中で生きてきた日本人にとって、魂の救済という答えは
個人課題ではなく先祖から子孫に繋がっていくみんなの課題であったはず。
「信じるものは救われる」=「信じない者は地獄行き」
といった、答えを個人の観念のみに帰結させてしまうキリスト教の欺瞞に、
当時の日本人は本能的に気づき、ザビエルが答えに窮するような
質問をぶつけたのではないでしょうか。
187: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:50:58.96 ID:NCHwEayer
>>2
草
まあ所詮(カトリックに限らず)「人工の宗教」だからな
別に無神論者ではないが「人の手が入った体系だった宗教」は信用出来ん
5: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:24:56.29 ID:jNbiaVU10
普通にキリシタン増えとったが
6: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:25:13.98 ID:cZSMXsJKM
ひろゆきの祖先やろ
9: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:26:06.36 ID:0meykNpD0
キリシタンって要は現代で言うポカホンタスのことだよな
11: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:26:23.08 ID:YHbYEey7d
長いから三行で要約すると
土人感覚で日本人に布教しようとしたら
白人より精神的レベルが高くて
ザビエルびっくり
14: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:26:30.88 ID:s1SY3CYZ0
こんな疑問誰でも思いつくやろ
24: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:28:49.20 ID:YHbYEey7d
>>14
北米「グエー」中南米「グエー」アフリカ「グエー」インド「グエー」東南アジア「グエー」中国「グエー」
日本人「そのキリスト教おかしくね?」ヨーロッパ「あばばばば」
45: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:32:07.84 ID:Krbw+BggM
>>24
別に北米もインドも中国も宗教で支配したわけじゃないし
北米は現地人あんまおらんし、インドも中国もキリスト教そんな信仰してないし
15: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:26:56.30 ID:BeuwAP7f0
キリシタン騙されやすいアホだった説
17: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:27:06.80 ID:mq2vVnzQ0
いやキリシタン増えて人攫いされてた定期
19: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:27:44.50 ID:zvR9q1I40
揚げ足取りだけは世界一上手い民族だからな
20: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:28:00.31 ID:2+qjWVmOd
女を奴隷として船で運ばれてたんだよね…
92: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:39:27.10 ID:uLCLEWXlr
>>20
豊臣秀吉自身が奴隷所有者だったんだよなぁ...
23: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:28:26.48 ID:e38J0CMwM
長崎の出島にきた白人が日本人を奴隷にして本国に送っててそれにキレた秀吉が宣教師追放令出したって経緯が教科書に載らないの闇だよな
26: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:28:56.95 ID:64Bnnswn0
これヨーロッパ含め世界中で突っ込まれてるからな
それで煉獄とかいう後付け設定生やした
27: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:29:08.40 ID:DsKLFQ4J0
このタイミングで鉄砲伝来していなかったらあっという間に植民地になっていた説あるよね
34: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:30:44.70 ID:mq2vVnzQ0
>>27
せやな
鎌倉以降は武士社会やからそこまでやろうけど
29: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:29:45.42 ID:GyBagEsu0
嘘つくな
侵略されかけてたからキリスタン禁止令出して守っただけじゃい
44: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:31:54.52 ID:YHbYEey7d
>>29
他のアジア諸国、アフリカ諸国、アメリカ諸国が次々やられてく中、日本だけは支配出来なかった模様
76: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:37:57.11 ID:jNbiaVU10
>>44
イギリスの傀儡だった長州と薩摩で明治政府作ったやん
31: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:30:20.04 ID:nQR8kzNDd
南無阿弥陀仏だけで救われるで
日本人「えっ!」
32: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:30:35.99 ID:PndO+7140
戦国時代から「それ貴方の感想ですよね?」があったのか
33: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:30:39.09 ID:QUaz87l30
実際キリストが産まれる前の人類はみんな地獄に落ちたって考えられてるの?
38: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:30:59.79 ID:XeiyJm/Da
普通にキリシタンは増えてた定期
ただキリストをお釈迦様、聖母マリアを如来などと勝手に仏教擁護でに置き換える独自解釈しだして宣教師の頭を悩ませてた模様
133: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:44:42.96 ID:YcEuprSa0
>>38
大昔からカレーうどんたらこパスタとやってること一緒やねんな
40: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:31:29.08 ID:U5F4ek0Ga
切支丹を潰してくれた秀吉と家康には感謝やな
41: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:31:34.30 ID:eozwWAGy0
庶民も宗論とか大好きだったんやね
48: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:32:58.27 ID:bQvSBP1y0
ヴォルテールはキリカスが調子乗って日本に嫌われたとか書いてたな
50: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:33:20.46 ID:BC3Yend90
松永久秀「詐欺だぞ」
52: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:34:23.60 ID:TG9EOQU90
当時の中国にも韓国にもって書いてるけど別に中国や朝鮮もキリシタン弾圧はしてたやん
キリスト布教を使っての侵略をされなかったってのを根拠にこういう逸話を言ってるならそれは中国や朝鮮にも当てはまる事やろ、何で中国朝鮮は失敗して日本だけが矛盾ついた!みたいに言うてんのや????
53: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:34:40.71 ID:3wqjziNR0
すぐ南のフィリピンはいつのタイミングで侵略されたんや?
キリスト教で英語使うやろ
70: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:36:56.83 ID:o9RccRPm0
>>53
1500年代半ばくらい
107: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:41:25.79 ID:Krbw+BggM
>>53
あいつらも武力で支配されて、植民地時代が長すぎて、文化も移されたパターンやからな
145: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:46:33.74 ID:wARnGywh0
>>53
比叡山が信長に燃やされたころにマニラに総督府作られてた
55: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:35:08.09 ID:o9RccRPm0
キリシタンが多かったのは九州各地の税の重さがほぼ原因やろな
58: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:35:53.04 ID:im9fVbHD0
ザビエルが河童の元ネタなのは余り知られてはいない
60: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:35:58.90 ID:XjaYPGvt0
というか日本は元々そういう一神教的な「真理」なんてない
漢字を訓読みと音読みにわけるという特殊な言語体系な時点でジャック・ラカンは「日本人は倒錯者」言ってる
188: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:51:01.28 ID:TG9EOQU90
>>60
日本すげええええええ
61: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:36:17.63 ID:LGNwwD/E0
仏教も厳しい修行をして極楽浄土へ行けるって教えやったんやろ
信者獲得のために祈ればOKになって最後は何もしなくても誰でも行けるようになった
63: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:36:24.70 ID:Qx5EzeDd0
そもさんせっぱだろ
問答があったからこそ
突き詰めると仏教が一番まともな真理なんだろな
68: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:36:43.30 ID:VT2puhJn0
キリスト教のカスってマジでこんなもん信じてるの?
アホでも引っかからんレベルやろ
72: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:37:22.99 ID:cmPKKg7S0
南米で大虐殺してた時に日本来てて同時期なんだよな
何で日本だけ普通に交易してたんだ
82: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:54.93 ID:XjaYPGvt0
>>72
遠過ぎて本国から軍隊出せなかっだけでは
104: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:40:43.38 ID:xL8aOREq0
>>72
せやから布教しようとしたイギリスとかはガン無視して宗教より貿易優先のオランダと国交するようになるやん
78: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:30.01 ID:LlwvdoUd0
隠れキリシタンやってるうちに土着信仰とどんどん融合して明治の頃にはキリスト教とはまったく違った宗教になってて話好き
84: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:58.24 ID:o9RccRPm0
>>78
いまだに隠れキリシタンやってんのは闇
95: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:39:49.07 ID:LlwvdoUd0
>>84
ご先祖様以来の信仰やからしゃーない
80: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:48.70 ID:hSDshG8i0
でもハゲてるじゃん
81: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:52.09 ID:f7sEdIDY0
宣教師「めんどくせーな…せや神を疑う事は罪ってことにしたろ!」
83: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:38:55.06 ID:VsdIiYsq0
オランダ人がスペインを信用するな侵略の手先と助言したんじゃなかったか
87: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:39:04.90 ID:zloNG8FQd
キリスト教の人は他の宗教の奴はみんな地獄へ行くと思ってんの?
91: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:39:26.32 ID:QClekEM50
これは嘘だと思うが実際普及しなかったから豊臣の勝ち
94: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:39:45.58 ID:mLeBPVIgM
なおキリスト教国の黒船来襲にはビビってしまった模様
101: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:40:35.02 ID:o9RccRPm0
>>94
やっぱ神より暴力のが怖いわ
116: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:42:27.13 ID:VsdIiYsq0
>>94
太平の期間が長すぎたんや
戦国時代がヤバすぎる。
鉄砲が伝わってからある程度立つとヨーロッパ全土の総数よりも量産されてたとか
100: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:40:32.66 ID:WxbytAmc0
あなたの信じている神様というのは、ずいぶん無慈悲だし、無能ではないのか。
全能の神というのであれば、あなたの髪ぐらい救ってくれてもいいではないか
103: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:40:42.89 ID:5qlcng8+p
遠藤周作の沈黙の映画のイッセーおがたがかっこいいよ キリスト教は日本人の身体には合わない服なのじゃみたいなこと言ってる
112: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:41:47.89 ID:hd7Q8mUHM
なお改宗した人間を奴隷として扱っていた為秀吉にブチギレられる模様
115: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:42:23.68 ID:v00Ch2KLM
神を試してはならない
これ敗北宣言やんな?
119: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:42:51.16 ID:LlwvdoUd0
ガキの頃読んだ歴史漫画だと島原の乱が敬虔なキリシタンによる宗教戦争みたいに描いてる無茶苦茶なのあったな
120: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:42:52.37 ID:Yxlb4K0p0
鉄砲の所有数で見ると世界有数の軍事大国だったんだろ
122: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:43:04.70 ID:34S0KXZ2a
中韓にもキリスト教広まってないやん
雑魚やん
134: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:44:46.60 ID:v00Ch2KLM
>>122
韓国はキリスト教徒多いぞ
クソ宗派やが
137: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:45:34.77 ID:o9RccRPm0
>>134
赤い十字架こわい
149: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:47:02.35 ID:7tLZ2KUuM
>>122
日本にあるキリスト教会とか主催者韓国人だらけやぞ
167: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:48:26.39 ID:LlwvdoUd0
>>149
教会の前の今週のミサのテーマみたいの見ると韓国人名の牧師担当多いよな
136: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:45:14.65 ID:xL8aOREq0
そういや天下統一されて戦がなくなった武士が海外に雇われて戦線に投入されて結構頑張ったみたいな話どっかで聞いたな
ソース忘れたけどどこかに転がってへんやろか
140: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:45:54.52 ID:izlUaRg70
日本は天災で何度も我に返るからなぁ
146: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:46:37.69 ID:v00Ch2KLM
>>140
数年おきにやっぱ神様なんておらんやんけ!って実感させられるのは強いわ
159: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:47:48.35 ID:1Zk6PdR1d
>>146
天災は神道とかでは神の怒りとかなんやないの?
175: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:49:44.43 ID:v00Ch2KLM
>>159
悪い神様の仕業や
だから祀って機嫌取って悪さしないようにお願いするんや
Godを神って訳したのは悪手やわあっちとは意味合いが違う
148: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:46:56.45 ID:DadYjEwx0
今のインフルエンサー(笑)に胸酔する連中みてるとホンマかどうか疑わしいけどな
154: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:47:21.00 ID:LlwvdoUd0
途中から「あーもうお前がキリシタンでもええからここは踏み絵踏んだ振りだけしとけ」とか言い出してるのホンマ好き
176: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:49:54.23 ID:g8/+qbns0
>>154
裁く側も「頼むから踏んでくれー!」って思ってたらしい
前線で実際に処刑する人達には信仰の違いで死刑はかなりメンタルにダメージがあったんやって
157: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:47:47.57 ID:rpOMw0/Qd
ブッダ「神なんておらん自分を高める修行しなはれ」
日本人「はえーブッダさん拝んでおこぼれもらお」
204: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:54.44 ID:nQR8kzNDd
>>157
修行はきついからしゃーないね
165: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:48:16.64 ID:mq2vVnzQ0
嘘か本当か知らんけど
天動説教えた時も太陽が中心なのは当たり前やんってなったとかなんとか
アマテラスが太陽神やからまあ全くの嘘でもない気はするが
171: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:48:54.42 ID:I3KbChew0
レスバ弱すぎるやろ
177: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:49:59.43 ID:K8G1Rm2x0
寺子屋のおかげで識字率は圧倒的だったのは事実だし。知識、文化水準が
高くても何ら不思議はないだろ。
180: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:50:14.76 ID:xvsxoc3qr
異国の地に宗教広めようとしてる奴がそんなレスバ弱くてええんか?
200: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:44.75 ID:lFTKn9I6a
>>180
当時のイエズス会なんて低知能の未開土人にありがたい教えを授けてやるってスタンスやし
わざわざレスバの素振りしてくわけないやん
191: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:51:24.95 ID:b+Q7zDuua
仕事上手いこと進まんかったから自演したんやろこのハゲ
197: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:15.22 ID:NCHwEayer
>>191
草
言い訳モードかい
196: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:08.50 ID:0ISjfn/j0
そんなアホなキリスト教が文化も武力も覇権になったのはなんでなんや?
199: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:34.69 ID:QaxUbhJta
なおキリシタン大名
202: 名無しさん 2021/08/20(金) 06:52:50.33 ID:kppILpkxd
ワイらの先祖も火の玉ストレートぶつける煽りカスで安心したわワイは悪くない