[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「大豪族は部族の兵力をもち、部族員たる小作人の生産を搾取する一種の独立国だったが、それが分解して中・小豪族ばかりになると、互いに連合するか、大勢力のもとに依存するかで、地位の安全を保つしかない。これは中央集権的な組織に編成されやすい。私は、それを蘇我稲目・馬子が行ったと思っている。いうなれば、大化改新の官僚組織は、蘇我氏が準備し、孝徳・天智朝が蘇我蝦夷・入鹿を滅ぼしてそれを横取りしたのだと推定している。蘇我氏が自己中心的にすすめていた官僚体制を天皇家が奪取したのが『大化改新』だったのだと考える(蘇我氏が『大王』だったという一部の説は成立しない。『大王』になれるのは新羅の真骨と同じく、その血族でなければ他に承認されなかった。大王家に比すべき勢力と、大王の資格を混同してはならない。」
小林恵子の「二つの顔の大王」に、皇極女帝(宝王女)が舒明と結婚する前に高向王と結婚し一児を得ている、その高向王とは高向玄理ではないか、という説を出している。さらに、高向玄理は韓国人だっただろうとしているが、これは大いに蓋然性がありそうである。つまり、「高」姓である。
もしそうだとすると、高向玄理は思いがけない重要人物だ、ということになる。あるいは大海人皇子か中大兄皇子の父親ということになるかもしれない。大化の改新の時に暗殺現場を見た何とか皇子が「韓人が入鹿を殺した」と言ったというのも、中大兄皇子あるいは(暗殺実行者の)大海人皇子が韓人であるのは周知のことだったから、となるわけだ。
ちなみに、下記記事の「隋へ留学する」は、高向玄理(ら)が韓国人で中国の文明に詳しいからこそ選ばれたと見ることができる。
留学からの帰国後5年目で大化の改新が起こったというのも暗示的である。
またたとえば大海人皇子もその留学に同行していた、というのも考えられる。皇極が高向王との間に産んだ漢王子が大海人皇子であり、最初は(父親の出自のために)皇位継承資格が低かったから、父親と危険な海外旅行に同行する決意をするのも容易だった、というわけだ。
かなり話が錯綜してきたので、いずれ年表や相関図を作ってみたい。
高向玄理
高向 玄理(たかむこ の くろまろ、生年不詳 - 白雉5年(654年))は、飛鳥時代の学者。名は黒麻呂とも記される。高向古足の子[1]。姓は漢人のち史。冠位は大錦上。
出自[編集]
高向氏(高向村主・高向史)は応神朝に阿知王とともに渡来した七姓漢人の一つ段姓夫(または尖か)公の後裔で[2]、魏の文帝の末裔を称する渡来系氏族[3]。一説では東漢氏の一族とする[4]。高向の名称は河内国錦部郡高向村(現在の河内長野市高向(たこう))の地名に由来する[5]。
経歴[編集]
遣隋使・小野妹子に同行する留学生として聖徳太子が選んだと伝えられており、推古天皇16年(608年)に南淵請安や旻らとともに隋へ留学する[6]。なお、留学中の推古天皇26年(618年)には、隋が滅亡し唐が建国されている。舒明天皇12年(640年)に30年以上にわたる留学を終えて、南淵請安や百済・新羅の朝貢使とともに新羅経由で帰国し、冠位1級を与えられた[7]。
大化元年(645年)の大化の改新後、旻とともに新政府の国博士に任じられる[8]。大化2年(646年)遣新羅使として新羅に赴き、新羅から任那への調を廃止させる代わりに、新羅から人質を差し出させる外交交渉を取りまとめ[9]、翌647年(大化3年)に新羅王子・金春秋を伴って帰国し、金春秋は人質として日本に留まることとなった(この時の玄理の冠位は小徳)[10]。大化5年(649年)に八省百官を定めた[11]。白雉5年(654年)遣唐使の押使として唐に赴くこととなり、新羅道経由で莱州に到着し、長安に至って3代目皇帝・高宗に謁見するものの病気になり客死した[12]。
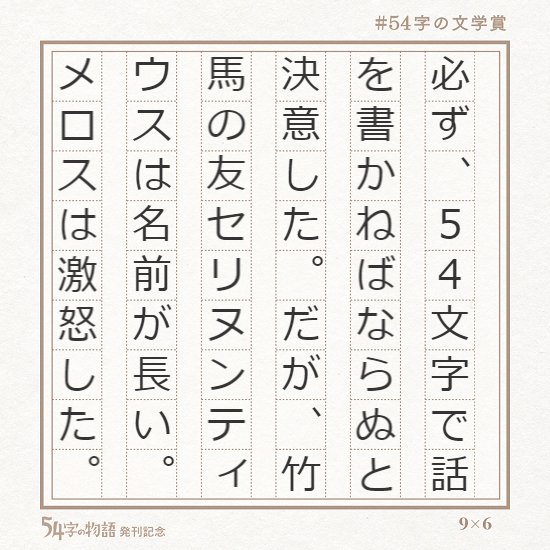
特に面白かったのは戸川幸夫の「明治の気概」という小説で、小説と言うよりほとんど事実に基づいた内容だと思われる。戸川幸夫は動物文学で有名だが、ファンタジー系の動物文学ではなくリアリズム重視の作風だから、人事を描いても事実を重視するのだろう。
日露戦争の細部を知る上で役に立ったのは、太平洋戦争研究会という集団が書いた「(キーワード)日露戦争と明治日本」という本で、コンビニなどで売っていそうな豆知識本に見えるが中味は相当に充実している。ただ、地図が少ないので、戦争の状況がイメージしにくい。人物の写真などより地図や戦争要図(略地図)の見やすいものを載せてほしかった。
日露戦争の地理的把握という点で役に立ったのは中公新書の横手慎二著「日露戦争史」に載っていた「日露戦争要図」である。この本は日露戦争に至るまでの日露の政治的状況を詳しく書いているところもいい。
何しろ、遼陽とか奉天とか言われても、アジア大陸のどのあたりか私には分からなかったのであり、大多数の日本人はそうなのではないか。そもそも満洲がどのあたりにあり、そこがなぜ問題視されたのか、現代の人間には分からない。高校や中学で日露戦争を習う生徒たちも同じだろう。
黄海海戦の黄海とはどこかも分からないし、対馬海戦の対馬がどういう位置にあるのかも分からない。朝鮮半島の地形もさっぱり分からず、山や平野や川の位置も分からない。
こんなことなら中学校や高校で購買させられた地図帳を大事に取っておくのだったと思っても、その当時は地理などにまったく興味は無かったのだから入試が終わると即座に捨てたのも当然である。
とにかく、歴史は地理や政治経済と同時に学ばないとまったく意味も分からないしイメージ化もできない。それが社会科教育の根本欠陥だろう。授業の時には参考資料が机の上に数冊置いてあるというのが社会科の授業であるべきだ。
まあ、今の子供たちはウィキペディアがあるだけマシであるが、授業中にネットで調べていいという教師はまずいないだろう。それをやったら、自分がいかに無知でいかにいい加減なことを教えているか生徒たちに即座に知られてしまうからである。
簡単に日清日露戦争の総括をしておけば、この両戦争は太平洋戦争とは異なり、「日本が近代国家(先進国家)の仲間入りをするためには」避けられない戦争だったと思う。もちろん、近代国家にならなくてはいけないということもないので、その意味では不要な戦争だっただろう。しかし、当時の日本の政治家や軍人たちは、日本が近代化し国力(軍事力)を増進しないと欧米大国によって植民地化されるという恐怖は大きかったと思うし、また実際そうなる可能性は大きかったと思う。
では、この両戦争に踏み切ったその判断は正しかったか、と言えば、私は疑問に思う。
たとえ一時的に植民地化されても、日本人の知的水準ならやがて独立することも可能だったのではないか。結局、この両戦争で国民(日本だけでなく朝鮮や中国やロシアの国民)の払った犠牲の大きさを考えれば、それは欧米の植民地になることによるマイナスよりマシだったかどうか分かったものではない。しかも、それは戦争に勝った上での話であり、負けていたらどうなっていたことか。結果が良かったから日清日露戦争に踏み切ったのは正解だ、とは言えないだろう。そういうのをまさに結果論と言うのである。
この両戦争に勝った結果野放図に膨れ上がった日本の軍人の夜郎自大体質がやがて日本を太平洋戦争の泥沼に引きずり込んでいったのは誰でも知っていることである。一時の勝利(成功体験)は、未来の危険の種なのである。
常備排水量の概算式は一見すると小難しいが、単なる掛け算であり、おそらく水線長が喫水線部分の船体の縦の長さ、水線幅が同じく横の長さ、吃水が船の喫水線から船底までの長さ、方形係数は、上記の3つの数字の積が直方体であるのに対して、船の喫水線下の部分の形状(大雑把に言えば三角柱だが、半楕円形柱とも言える)がどのくらいの比率かの数字だろう。そして、一番最初の数字は海水の比重だと思う。
(以下引用)
なお常備排水量については、下記のような概算法が知られている。これによって、実際の値の95 - 98パーセント程度の近似値を得ることができる[1]。
- :常備排水量
- :水線長
- :水線幅
- :吃水
- :方形係数 (駆逐艦では一般的に0.47 - 0.52程度)
種類[編集]
艦船の状態によって排水量は異なるため、以下の通り複数のものがある。なお、以下で「水」とあるのは飲料水その他の生活用水ではなく、予備罐水、つまり蒸気機関で使用する補充用の水のことである。
軽荷排水量[編集]
軽荷排水量(英: light displacement)は、弾薬・燃料など全ての消耗品を搭載しない状態の排水量。なお、実際にこの状態で航行すると復原性が低下することから、バラストタンクに注水して重心を下げることになるが、これを補填軽荷排水量(ballasted light displacement)と称する[1][3]。
基準排水量[編集]
基準排水量(英: standard displacement)は、満載状態から燃料と予備水を差し引いた状態の排水量[1][3]。
年代および国によって定義が異なるが、一般的にはワシントン海軍軍縮条約において採用された上記の定義が用いられる。仮想敵国から想定される作戦海域は各国で異なり、燃料および予備缶水を含めると長大な航続力を必要としない国が有利になることから、純粋な戦闘能力のみで比較するためにこれらの重量を差し引いた状態とされた。想定作戦海域が広大である英米が不利にならないためであるとも言われている。船の状態としては不自然に過ぎ実用的ではないため、近年ではこの状態を諸元として使用する国はない。
なお、海上自衛隊は艦艇の公式諸元として基準排水量を公表しているが、これは名称こそ同じであるものの、1978年(昭和53年)に制定された船舶設計基準細則で規定されているものである[4]。
常備排水量[編集]
常備排水量(英: normal load displacement)は、乗員と弾薬は定数を、また燃料・真水・糧食などの消耗品は3分の2を搭載した状態の排水量。戦場(目的地)に到着したときの状態を想定したものである。ワシントン条約締結以前は、これを排水量の標準として使用する国が多かった。
イギリスではかつて積載排水量と、また大日本帝国海軍では公試排水量と称していた。なお大日本帝国海軍の場合、大正時代末期までは、公試排水量とは別に、弾薬3/4、燃料1/4、水1/2の搭載状態を常備排水量として定義していた[3]。
満載排水量[編集]
満載排水量(英: full load displacement)は、乗組員・弾薬・燃料・水など、計画上搭載できるもの全てを搭載した状態での排水量[1]。ただしバラスト水は半量とする[3]。近年多くの海軍ではこれを公式の諸元として使用している。






