現存する最も古いサーファーの写真。 http://bit.ly/2Zx352j 1890年にハワイ・オアフ島のワイキキで撮影されたもので、人はポリネシア系の先住民、背後の山はダイヤモンドヘッド。サーフィンはポリネシアの伝統だったが、入植した白人が悪習として弾圧し、19世紀末には消滅寸前に。今とは隔世の感。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「欲望のあいまいな対象」は見ていないが、面白い題名だと思う。正確には「欲望のあの曖昧な対象」と訳すべきだと思うが、スペイン語原題(があるかどうか知らないが)がどうなのか。
「that」が入るかどうかはわりと重要な気がする。つまり、「欲望のあいまいな対象」全体をぼんやりと問題視しているのではなく、「あの」と強調しているわけだ。つまり、このobjectは特定のものなのか、それとも一般的に見て欲望というものの対象はあいまいなものだということかが問題だ。
そして、映画監督(ブニュエル)の意図が前者だとしても、後者だとしたほうが、哲学的には面白い。哲学は物事を抽象して思考するのであり、特殊事例(抽象化で捨象される)を論じる意味はないからだ。
江戸小話に、大きな商家の箱入り娘が恋煩いしたらしいということで、その相手が誰か調べるように言われた番頭(か乳母)が、相手は誰か娘に聞くと、しばらくモジモジした後で、「誰でもいいの」と答えたという笑い話があるが、案外、人生の実相、あるいは恋愛心理の実相を突いているかもしれない。
要するに、誰かを見て(知って)突然恋をするのではなく、「恋への憧れ」が先にあって、それに良さそうな誰かを見て「この人だ!」と思うのではないか。
欲望そのものがあいまいだという考えもでき、ロリコンが一般化しなかった時代には、幼女に性的欲望を抱く人間はほとんどいなかったのではないか。つまり、「我々は欲望を学ぶ」のである。
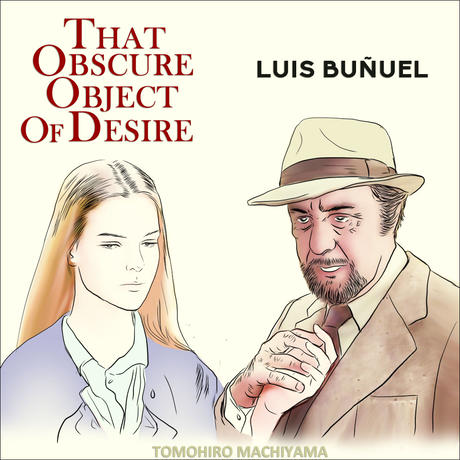
「that」が入るかどうかはわりと重要な気がする。つまり、「欲望のあいまいな対象」全体をぼんやりと問題視しているのではなく、「あの」と強調しているわけだ。つまり、このobjectは特定のものなのか、それとも一般的に見て欲望というものの対象はあいまいなものだということかが問題だ。
そして、映画監督(ブニュエル)の意図が前者だとしても、後者だとしたほうが、哲学的には面白い。哲学は物事を抽象して思考するのであり、特殊事例(抽象化で捨象される)を論じる意味はないからだ。
江戸小話に、大きな商家の箱入り娘が恋煩いしたらしいということで、その相手が誰か調べるように言われた番頭(か乳母)が、相手は誰か娘に聞くと、しばらくモジモジした後で、「誰でもいいの」と答えたという笑い話があるが、案外、人生の実相、あるいは恋愛心理の実相を突いているかもしれない。
要するに、誰かを見て(知って)突然恋をするのではなく、「恋への憧れ」が先にあって、それに良さそうな誰かを見て「この人だ!」と思うのではないか。
欲望そのものがあいまいだという考えもでき、ロリコンが一般化しなかった時代には、幼女に性的欲望を抱く人間はほとんどいなかったのではないか。つまり、「我々は欲望を学ぶ」のである。
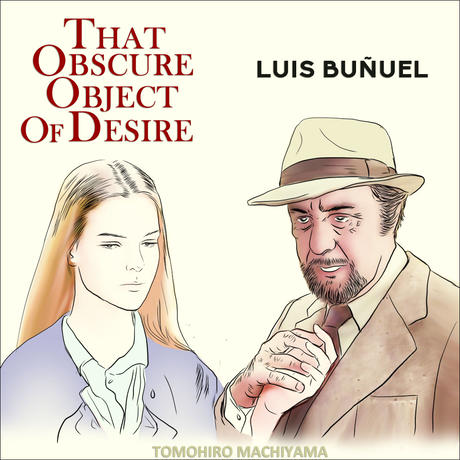
町山智浩の映画ムダ話140 ルイス・ブニュエル監督『欲望のあいまいな対象』(1977年)。資産家マチウは美しいメイドのコンチータを愛人にしようと追い回すが……。2人の女優が交代で演じる一人の……。
¥216 税込
※こちらはダウンロード商品です
ThatObscureObjectOfDesirePoster.mp3
38.4MB
町山智浩の映画ムダ話140 ルイス・ブニュエル監督『欲望のあいまいな対象』(1977年)。資産家マチウは美しいメイドのコンチータを愛人にしようと追い回すが……。2人の女優が交代で演じる一人のヒロイン、貞操帯、多発するテロ、謎のズタ袋に秘められた意味は?
PR
サーフィンがポリネシア発祥の「土人のスポーツ」(笑)だったこと、白人に弾圧されて消滅しかかったことも面白いが、写真の中の情報も面白い。この先住民男性の体に無駄な脂肪が無いこと、褌というのは日本だけでなくポリネシアの風俗でもあったことなど。
-
近藤ようこさんがリツイート
日本では韓国ドラマのリメイクがかなり作られているが、ほとんどヒットしない、という話である。それなら、リメイクではなく吹き替え版か字幕版でいいのではないかと思うが、実は日本の芸能界でカネを使うこと自体に意義があるわけで、吹き替え版ではカネを使う要素が少ないから嫌われるのだろう。つまり、日本芸能界維持のためのプロジェクトがリメイクドラマであるわけだ。それによって芸能界やその周辺の人々にカネが落ちる。
視聴率の低さについては、単純に「ドラマの根底の精神が日本人にはピンと来ない」ということかと思う。
日本人と韓国人は顔はそっくりだが、気質的な微妙な違いがあり、それが、表面が似ているほど些細な違いが不気味に思われるという「不気味の谷間」になる気がする。簡単な話、日本人だと思っていた相手が韓国語を喋り出した瞬間に、その「不気味の谷間」が生まれるのである。
韓国人に限らず、私は異国人のすべてに「できれば敬遠したい」という気持ちを持っている。白人に関しては、ハリウッド映画と米国テレビドラマで育ったからその気質や文化に慣れ親しんでいるせいであまり不気味さを感じないのだが、アジア人にこそその不気味の谷間があるのである。ある意味、自分が白人ならアジア人にこう感じるだろう、という不気味感を勝手に白人と共有しているとも言える。
顔が似ているのにまったく別人種というのは、なかなか厄介である。
「ボイス 110緊急指令室」(日本テレビ系)でいうと、真木よう子の演技が空回りしていて、せっかくのストーリーが頭に入ってこない。
14年に韓国で放送され、社会現象となったドラマ「ミセン-未生-」(ケーブルチャンネル)を原作にした「HOPE~期待ゼロの新入社員~」(フジテレビ系)が16年に放送された時もダメだった。人気絶頂のHey!Say!JUMPの中島裕翔(26)を主演に持ってきたにもかかわらず、視聴率は6%台に終わった。
原作はリストラや女性の社会進出など、社会問題を忠実に再現した設定や、説得力のあるセリフが満載の重厚な社会派ドラマだったのに、日本でのリメイク版は演出が悪かったのか、視聴者の気持ちを全く掴むことができず、薄っぺらい恋愛ドラマ仕様に仕上がってしまったことが敗因だろう。
視聴率の低さについては、単純に「ドラマの根底の精神が日本人にはピンと来ない」ということかと思う。
日本人と韓国人は顔はそっくりだが、気質的な微妙な違いがあり、それが、表面が似ているほど些細な違いが不気味に思われるという「不気味の谷間」になる気がする。簡単な話、日本人だと思っていた相手が韓国語を喋り出した瞬間に、その「不気味の谷間」が生まれるのである。
韓国人に限らず、私は異国人のすべてに「できれば敬遠したい」という気持ちを持っている。白人に関しては、ハリウッド映画と米国テレビドラマで育ったからその気質や文化に慣れ親しんでいるせいであまり不気味さを感じないのだが、アジア人にこそその不気味の谷間があるのである。ある意味、自分が白人ならアジア人にこう感じるだろう、という不気味感を勝手に白人と共有しているとも言える。
顔が似ているのにまったく別人種というのは、なかなか厄介である。
韓国ドラマのリメイク版が日本でヒットしない決定的な理由
公開日: 更新日:
なぜ、韓国で大ヒットし、人気を約束されていたはずのリメイク版ドラマが奮わないのか。シナリオ自体に問題はないのだが、やはりそこには、役者の演技力であったり、社会的な背景が日本人の感覚に合わないということが考えられる。
「ボイス 110緊急指令室」(日本テレビ系)でいうと、真木よう子の演技が空回りしていて、せっかくのストーリーが頭に入ってこない。
14年に韓国で放送され、社会現象となったドラマ「ミセン-未生-」(ケーブルチャンネル)を原作にした「HOPE~期待ゼロの新入社員~」(フジテレビ系)が16年に放送された時もダメだった。人気絶頂のHey!Say!JUMPの中島裕翔(26)を主演に持ってきたにもかかわらず、視聴率は6%台に終わった。
原作はリストラや女性の社会進出など、社会問題を忠実に再現した設定や、説得力のあるセリフが満載の重厚な社会派ドラマだったのに、日本でのリメイク版は演出が悪かったのか、視聴者の気持ちを全く掴むことができず、薄っぺらい恋愛ドラマ仕様に仕上がってしまったことが敗因だろう。
狂歌師の名前で、「文反古継剥(ふみほうごつぎはぎ)」を、別の漢字表記で表す。「つぎはぎ」は「月萩」など。「ふみほうご」は考慮中。
現代でも十二分に通用する絵だと思う。
だが、御厨さと美は、話を作る才能はまったく無かったと思う。それを自分でも分かっていたのか、わずか数作で漫画家を廃業したと記憶している。
原作付きで漫画を描くという手もあっただろうが、彼の絵のキャラに合う原作を書けた人は当時はいなかったのではないか。辛うじて、手塚治虫か石森章太郎くらいか。だが、そういう大御所は、よほどの事情が無いと自分以外の絵柄で原作だけ書くということを承知したとは思えない。
だが、御厨さと美は、話を作る才能はまったく無かったと思う。それを自分でも分かっていたのか、わずか数作で漫画家を廃業したと記憶している。
原作付きで漫画を描くという手もあっただろうが、彼の絵のキャラに合う原作を書けた人は当時はいなかったのではないか。辛うじて、手塚治虫か石森章太郎くらいか。だが、そういう大御所は、よほどの事情が無いと自分以外の絵柄で原作だけ書くということを承知したとは思えない。
山本貴嗣さんがリツイート
日本のマンガのキャラクターが鼻が描かれない、もしくはかんたんな点か線になっているという件。私は子供の頃見た御厨さと美キャラの女性の鼻と口の描き方がカッコよくて衝撃を受けたなあ。当時、けっこうマネしたものです。 (=´ω`)
プロフィール
HN:
冬山想南
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
P R





