さよならジュピターは もっと面白くなっても良いと思うのだけれど 仲のいい人が集まって映画作るときの失敗の見本、みたいな感じなのでは。 当時のこと全く知らないので適当に書いてますけど。いろんな人の顔を立てて盛り込み過ぎて 色んな場面とか出番を引き算出来ない、みたいな
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
だが、映画は技術的に描けるものと描けないものがあるし、長さが決まっている。
とすると、大事なのは足し算ではなく引き算になる。足し算をしていいのは、元ネタが短編小説である場合などで、ヒッチコックの「鳥」の原作は短編小説だし、「座頭市」は、あるエッセイの一文を膨らませたものであるという。要するに、「盲目の按摩で、剣客でもある者がいた」というだけの事実を膨らまして映画にしたわけだ。
なお、SF映画というのは、特撮技術だけでなく、俳優の演技やメーキャップも大事で、邦画のSFはその点ではほぼ全部落第である。内容に架空性が強いほど、小さな部分の手抜きで架空性(作り物性)が意識され、観客がしらけるのである。
これは時代劇も同じなのだが、黒澤映画などではさすがに細部に手抜きが無いから、観客をすんなり映画の中に入り込ませる。おそらく、「用心棒」の最初に三船敏郎が登場する場面では、彼の着る衣服にちゃんと「汚し」を入れて、長旅で着古した感じを出していると思う。それが白黒映画でも観客には伝わるのである。
 tarafuku10 @tarafuku10
tarafuku10 @tarafuku10
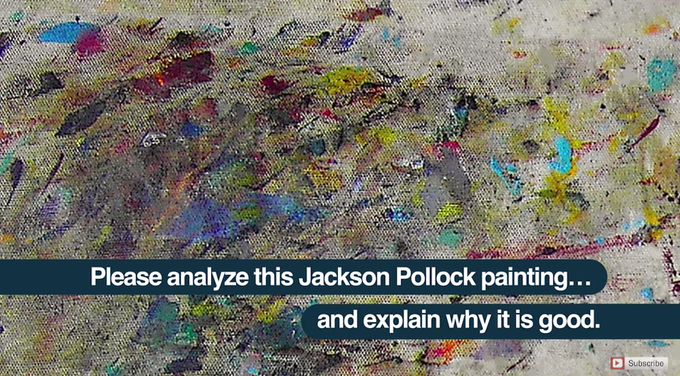 拡大
拡大 tarafuku10 @tarafuku10
tarafuku10 @tarafuku10

「赤毛のアン」が、新聞記事が一番最初の創作動機になったことはあまり知られていないと思う。確か、孤児院から養子を貰ったが、依頼したのと別の子供が「配送」されたという記事ではなかったかと思う。つまり、「赤毛のアン」の始まりとまったく同じ状況だ。だが、それ以前から創作意欲は身体に漲っていて、何を書こうか迷っていたところに、その記事が「燃料に点火した」わけだ。そして、この作品の凄いところは、発端の事件以上に面白い出来事が次から次へと起こっていくという、作者の想像力の豊かさと、「作中の人間が生きている」ことだ。
 弓月 光 @h_yuzuki
弓月 光 @h_yuzuki
夕刊の隅っこの五行くらいのニュースでも結構人の心に残る漫画になりますから、何にでもアンテナ広げて置いて損はないです
-
今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す
-
「トラブル急行2巻」に掲載の「3DKのサバイバル」です(すてま)https://twitter.com/sodium/status/1192695395945603072 …
「夜の想い」あるいは「夜の思想」あるいは「夜の思想群」という題名は非常に好きで、確かに昼の思想と夜の思想は違うよなあ、と思ったものである。
The Complaint:または、Night-Thoughts on Life、Death、&Immortalityは 、単にNight-Thoughtsとして知られていますが、 エドワードヤングによる長い詩で 、1742年から1745年の間に9部(または「夜」)で公開されています
詩は空白の詩で書かれています 。 それは、彼が妻と友人の喪失を熟考し、人間の弱さを嘆く一連の9つの「夜」にわたる死に関する詩人の黙想を説明しています。 詩の中で最もよく知られている行(「Night I」の最後)は、「原罪は時間の泥棒です」という格言です。これは、詩人が人生と機会がどれほど早く逃げることができるかを議論する一節の一部です。
Night-Thoughtsは出版後何年もの間非常に高い評価を得ていましたが、1797年にウィリアム・ブレイクによる一連の主要なイラストで最もよく知られています。1799年にトーマス・ストザードによってあまり知られていないイラストが作成されました。
9泊はそれぞれ独自の詩です。 それらは「生、死、不滅」( アーサー・オンスローに捧げられた)です。 「時間、死、友情」( スペンサーコンプトン専用); 「ナルシッサ」( マーガレットベンティンク専用); 「キリスト教の勝利」( フィリップ・ヨーク専用)。 「The Relapse」( ジョージリー専用)。 「The Infidel Reclaim'd」(2つのパート、「Glories and Riches」と「The Nature、Proof、and Importance of Immortality」。HenryPelhamに捧げられます)。 「美徳の謝罪;または、答えられた世界の男」(献身なし); そして「慰め」( トーマス・ペルハム・ホールズに捧げられた)。
ジェームス・ボズウェルは、 サミュエル・ジョンソンの生涯で 、 ナイト思考を 「人間の天才がこれまでに生み出した最も壮大で豊かな詩」と呼んだ。

