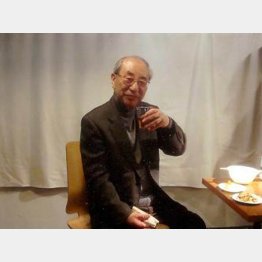[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(以下引用)
社会ファシズム論
| 共産主義 |
|---|
 |
社会ファシズム(しゃかいファシズム、ドイツ語: Sozialfaschismus、英語: social fascism)[1]とは、社会民主主義をファシズムと同一であるとする見解による用語で、ファシズム勢力より社会民主主義勢力への敵対と打倒を優先すべきとする。その主張および運動方針は、社会ファシズム論[2]または社会民主主義主要打撃論とも言われる。
1920年代後半から1930年代前半に、ヨシフ・スターリン、コミンテルンの支持で各国の共産党が主張し、特にナチス伸張期のヴァイマル共和国時代のドイツ共産党の実践によって顕著であった。しかし結果的にはNSDAPがドイツの政権を獲得し、ドイツ共産党が非合法に追い込まれたため、この方針への反省がおこなわれ、1935年のコミンテルン第7回大会によって自己批判の対象となった。
概要[編集]
社会ファシズム論とは、社会民主主義とファシズムを双子として同一視する見解である。こうした見解が生じた背景としては、ドイツ革命直後のドイツ社会民主党とドイツ共産党の路線対立や、ネップ(新経済政策)後に左傾するソ連内部において、路線対立が先鋭化していたことなどが挙げられる。1924年9月にはヨシフ・スターリンが「社会民主主義とファシズムは対立物ではなく、双生児である」と定式化し、1928年の第6回コミンテルン執行委員会総会は、社会ファシズム論を明示した[3]。
この路線に従ってドイツ共産党はドイツ社会民主党を敵視し、そのために議会では反社会民主党的な行動を繰り返した。ドイツ共産党の武装組織「赤色戦線戦士同盟」が社会民主党党員を襲撃したり、「ヴァイマル政府反対」を掲げナチスの労働者組織と共闘してストライキを行ったりした。とりわけ1929年5月1日にベルリンで行われた共産党の非合法デモを社民党政権が取り締まったことに端を発する血のメーデー事件(31名死亡、数百人負傷、1200人逮捕という惨事になった)で社共対立は絶頂に達した[4]。
激しさを増す社共対立は、同じく反社会民主党の姿勢を打ち出すナチスを結果的に利することになった。世界恐慌下でこうした左派政党内の対立がみられたことは、大衆の彼らへの失望とナチスへの期待を助長させた。また、ナチス政権成立の直前までドイツ共産党とドイツ社会民主党の合計議席数はナチスを上回っており、両政党が連携していればもっとファシズムに対抗する効果的な方策を打ち出すことも可能であった。しかしドイツ共産党の指導者エルンスト・テールマンは「ナチスに政権を取らせよ。ナチスには政権担当能力などなく、そうすれば明日には共産党が政権を取るだろう」と語っていた。結果的には、1933年にヒトラー政権が成立し、「ヨーロッパ最強」と言われたドイツ共産党は弾圧によって暴力的に急速に解体されることになる。ナチス・ドイツ政府は、1935年3月には再軍備を宣言した。こうした中で、1935年のコミンテルン第7回大会では人民戦線戦術が採択され、反ファシズムのために諸勢力が結集する方針が示された。これにより社会ファシズム論は否定されることになった。
批判[編集]
スターリン主義と対立していたレフ・トロツキーは社会ファシズム論を批判し、ドイツ共産党と社会民主党は連帯してナチスに立ち向かうべきだと主張したが、スターリン主義に忠実だったドイツ共産党からは聞き入れられなかった。この件に関する論考は、トロツキー死後の1962年と1969年に「社会ファシズム論批判」として出版された。
(以下引用)
社青同解放派
思想[編集]
社青同解放派は「マルクス・レーニン主義」の原則を批判し、「マルクス主義の復権」を提唱する。このため党組織論では、レーニン主義の前衛党理論(外部注入論)を批判し、全世界プロレタリアートの共通利益に依拠する革命的マルクス主義の党建設を目指す。思想的立場としては、スターリン主義の一国社会主義論、トロツキズムの反スターリン主義、毛沢東思想、既成左翼の官僚主義などを批判し、プロレタリアの国際的団結を訴える。また日本の社会主義思想としては、労農派を評価した。
後に解放派の綱領的文章とされた1961年5月 滝口弘人による『共産主義=革命的マルクス主義の旗を奪還するための闘争宣言(草案)』では、「日本帝国主義の新たな国家独占資本主義的展開」では「プロレタリアが全階級的政治性を身につけて、階級闘争を徹底的に貫き、支配権力を奪取して、資本制社会を根底から転覆しつつあらたな共同社会を建設する道」しかないが、「各国社会民主党が、いわば近代的官僚主義で包囲された特殊利益の連合」であるため、「全世界プロレタリアートの共通利益にのみ依拠」する「偉大な真実の共産主義=革命的マルクス主義の創造的復活」が必要であるとする。また「自称他称の諸「トロツキスト」集団」や黒田寛一は「観念論による宗派主義」であり、「「反ブルジョアジー」が「反スターリン主義」の現実的基盤であって、その逆ではない。」とする。また「レーニン主義=ボルシェヴィズムの基底的原則は、マルクス主義の基底的原則を正確に逆立ちさせたもの」で、「第一インターナショナル規約前文冒頭の原則からの断固たる背反」であり、「スターリン主義の真実の批判者は、トロツキズムではあり得ない」とし、更には「現代革命に誠実たらんとする者にとって、その立場は「マルクス=レーニン主義」ではあり得ない。それは、はっきりとかつ徹底的に「マルクス主義」でなければならぬのである。」として、マルクス主義の復権を提唱した。そして「「労農派」マルクス主義の科学としての成果を断固として擁護し、強調し、いっそう発展させなければならない 」として、「日本社会党の内部に、共産主義=革命的マルクス主義の徹底的な純化をめざす公然たる組織的な分派の形成から始めるべき」と主張した[5]。
日本帝国主義の新たな国家独占資本主義的展開は(略)資本と労働の二大階級の、この反復して生起する緊張状態が、濃縮して相当長期に亘り継続するとすれば、つまり、その時にこそ、ブルジョアジーの為の直接的暴力にうち固められた帝国――ファッシズムの支配の現出を許すであろう(略)我々の実践上の現実的立脚点を示すスローガンはただ一つである。「全世界ブルジョアジーを打倒せよ!」
全世界プロレタリアートの共通利益にのみ依拠して(略)偉大な真実の共産主義=革命的マルクス主義の創造的復活のために
プロレタリアートが主体であることである。『共産党宣言』は明確にそのようなものとして書かれている(略)レーニンはこれを「逆立ち」させた。
スターリン主義の真実の批判者は、トロツキズムではあり得ない。(略)その立場は「マルクス=レーニン主義」ではあり得ない(略)「マルクス主義」でなければならぬのである。
スターリン主義の本当の批判者は、レーニン主義そのものの「逆立ち」を感受していた革命的マルクス主義者(略)ローザ・ルクセンブルグである。
我々が直接に注目すべきであるとするものは、「労農派」マルクス主義である。
プロレタリアートは、本質的に非合法的存在であり、あらゆる革命は、本質的に暴力的である。これを確認するものだけが共産主義者である。
来たるべき日本革命は、20世紀修正主義によってゆがめられてきた一切のエセ「共産主義」者を保守主義者として告発しつつ、マルクスとプロレタリア共産主義革命がどんなに偉大なものであるかを、全人類の前に、はじめてはっきりとみせつけるであろう!— 滝口弘人『共産主義=革命的マルクス主義の旗を奪還するための闘争宣言(草案)』1961年5月[5]
歴史[編集]
解放派は他の新左翼党派とは異なって労働者を中心とする潮流と、学生を中心とする潮流の二本立てで考えるのが理解しやすい。
創成期[編集]
- 1960年2月27日 日本社会党本部2階で日本社会主義青年同盟学生班協議会の結成が行なわれる。(これは前年来、早稲田大学を中心として活動してきた、東京社会主義学生会議が、社青同の組織に発展的に転化したものである。)
- 1961年5月 滝口弘人が『共産主義=革命的マルクス主義の旗を奪還するための闘争宣言(草案)』を社青同東大班機関紙『解放』NO.6号に発表。その後ナンバー・シックスと呼称され、解放派の綱領的文章と呼ばれる。
- 1962年12月 過渡的な前衛的組織を目指した秘密組織である共産主義者通信委員会(KTC)を結成。
飛躍の時代[編集]
- 日韓闘争(労学)、早大闘争(学)を主導。
- 1965年7月 都学連をブントや中核派とともに再建(学)。
- 1966年 全学連をブントや中核派とともに再建(学)。
- 1966年 東交反合理化闘争を主導、社青同東京地本の中軸となる(労)。
- 1966年9月3日 社青同東京地本大会で解放派と協会派が衝突(九三事件)。社青同中央を握る社会主義協会派により東京地本が分裂され、東京地本は独立する(樋口圭之介委員長)。全国各地は各地本内部で、主導権を争いながら共闘している(労)。
- 1968年 東大闘争の主軸を担う(学)。
- 1968年12月 革マル派が早大文連及び早祭実支配のため、解放派メンバーを襲撃。解放派は早大より追いだされる。延長戦として、1月、東大闘争のさなか、駒場の解放派も襲撃する。
- 70年安保に向かう、ベトナム反戦運動の高揚の中で、反戦青年委員会が当初は、社会党・総評の主導で結成される(社会党青年局長であった高見圭司が中心であった)が、「反戦」の主導権は次第に新左翼のほうに移っていく(労)。
- 1969年9月 革命的労働者協会(社会党・社青同解放派)が結成される。
- 革労協結成をめぐっては、(社会党都本部の三分の一を占めるほどの)反戦派の内、解放派の初期メンバーが中心になって結成した社会党内グループである「革同」(社会党革命同志会)との分岐の問題があった。ドイツ革命期における、早期の新党結成か、ぎりぎりまで社民内分派闘争を追及するか、と同様の問題である。「社民内外を貫く公然たる分派の形成」との表現は、この二面の止揚なのか妥協なのか。学生運動では数年前から事実上、単独党派として活動しているので、このあたりの問題にリアリティーが薄い。これは後の狭間派の分離の伏線でもあるという意見もある。
- 1969年 68年に三派全学連から中核派が離脱した後のいわゆる反帝全学連が機能停止に陥っていた中、「プロレタリア統一戦線の一翼としての全学連運動」をかかげた第二十回定期全国大会を開催し、ここに解放派系全学連が誕生した。初代委員長は早稲田大学の石橋興一。
- 1969年10月11月決戦 (当時の首相・佐藤栄作の訪米阻止に向けた一連の闘争)、生産性本部、工業倶楽部、首相官邸、自民党本部、NHKに突入。
- 1970年5月 社会党都本部占拠
- 1970年6月 安保決戦(工場からの反乱を政府中枢へ)
- 1970年11月 社会党大会、13名の除名に対する抗議闘争
- 1971年2月 協会向坂派系執行部が社青同第10回大会を単独開催。解放派系地本はこれを認めない声明を発表する。
- 1971年3月 パリ・コミューン百周年集会を全国各地で開催。
- 1971年5月30日 集会場で中核派系の全国部落研と衝突、以降組織全体で部落解放運動に関わる。
- 1971年6月 参議院選挙全国区に高見圭司が立候補14.6万票(次々点。1977年までに1人が任期途中で死亡したため、次点に繰り上げ)を獲得。選挙時のスローガンは「議会にゲリラを!」だった。
- 1971年9月、解放派系地本、同盟員は神奈川大学で独自に社青同第10回大会を開催、樋口圭之介を委員長とする執行部を選出。これ以後解放派組織は革労協と社青同の二本立てとなる。
党派闘争の激化(正面戦段階)[編集]
- 1972年4月28日 大阪城公園で革マル派部隊が解放派を蹴散らす。革マル派学生木下正人が死亡。この死は心臓麻痺によるもので、この結果の対立はいったん小康状態になる。
- 1972年11月8日 革マル派が早稲田大学で早大生川口をリンチで殺害。早稲田解放闘争が始まり。WAC(早大行動委員会)が結成され、革マル派は次々と自治会執行部から罷免される。再度、早大支配をねらう革マル派は学生集会を襲撃し出すが、自衛武装を始めたWACに、解放派、ブント等が助太刀に駆けつけ正面戦の対峙が続く。
- 1973年5~6月 早稲田大学で革マル派全国部隊を3度にわたり粉砕。
党派闘争の激化(アジト襲撃と病院送り段階)[編集]
- 1973年9月14~15日 深夜、新学期の直前、早稲田解放闘争の継続を恐れた革マル派150名が神奈川大学に泊り込んだ解放派部隊約50人に4時間にわたり夜襲をかける。この結果、解放派部隊のほとんどが入院という大きな打撃を受ける。このとき攻撃側のレポが2人捕まる。寮にいた現場指導部の永井啓之は、最大の目標は集めうる部隊でのキャンパスへの救援であると、レポへのリンチを制止し反撃の準備に全力で取り掛かる。早朝ぐったりしたレポ2名を運びだし放置する。この2名が死亡し、北條全学連委員長、永井啓之が指名手配されてしまう。
- 1973年9月16日 革マル派はWAC(早大行動委員会)を三越デパート屋上で襲撃
- 1974年 ガスの検針員を装った革マル派の襲撃部隊が滝口弘人他十人近くを襲撃(中延ハイツ事件)。一年後の1975年に報復として解放派は、革マル派全学連本部創造社に対して武装襲撃。
- 1975年6月24日 加藤登紀子(夫が「反帝全学連」結成の際歩調を合わせた解放派との縁で貸した、伊東)の別荘で会議中、水中銃などを手にした革マル派に襲撃され、元九州大学生で革労協福岡県委員会のリーダー、石井真作が殺され狭間嘉明が瀕死の重傷を負う(狭間の口元に手をあててきたので、咄嗟に息を止めたとの事)。報復としてこの後、10月8日に立正大で秋本を、それから三週間後の27日に東大で梅田をそれぞれ殺害。
党派闘争の激化(殺人段階に入る)と組織の変質[編集]
- 1977年2月11日 中原一が国電取手駅前で待ち伏せしていた革マル派の襲撃部隊に殺害される(革労協書記長内ゲバ殺人事件)。この結果、狭間ら学生委員会武闘派・PSD(プロレタリア統一戦線戦闘団)の軍事主義への押さえが弱まってしまう。対革マル戦が激化する中で、後の労対派となる潮流は革マル派に対して報復を唱えるものの、解放派本来のレーニン主義批判の立場を堅持、革マルという党派の持つ宗派的イデオロギーを徹底批判するなど、あくまでイデオロギー闘争を持って革マルという宗派の解体が重要であるというスタンスに徹する。その一方で、学生組織・戦闘組織に影響力を持つ狭間嘉明とその取り巻きらは、革マルという革命党派に敵対する武装反革命集団をテロルにて物理的に解体するための軍事組織を早急に強化する必要があると主張し、解放派が批判の対象としてきたレーニン的組織原則に屈服してしまうこととなる。更に、当日の運転手にスパイの疑いをかけ査問する(いわゆるヨーロッパ問題)。
- 1977年4月15日 革マル派幹部藤原隆義(杜学)他4名が乗車した印刷局のワゴン車を前後から車で挟み撃ちにして攻撃。右翼の街宣車のように鉄板で防御してあったので攻めあぐね、発炎筒を投げ込み、いぶりだしをはかるも失敗、時間切れのため撤収し、攻撃失敗と報告する。攻撃の衝撃でドアを中から開けることが出来なかったのか、積荷のインクが引火し4人は焼死。事件から二日後に行われた三里塚の集会にて革労協活動家が犯行を追認するビラを配布し事件の動機が明確になった。当初意図したこととは違う結果となったものの、残虐な軍事的手段をもって革マル4人の「死」をもたらしたこの襲撃は後の軍事路線の方向性を決めたという点で、解放派の重要な転換点になった事件である(浦和車両放火内ゲバ殺人事件)。
- 1978年10月 目上委差別ビラ事件問題発生。東京都目黒区において、映画「造花の判決」上映宣伝ビラの記載事項に「百歩譲って石川が黒だったとしても…」という記述が大きな批判を受けた。「目黒区上映委員会」=「目上委」は地域における地域の小さなサークルであり、批判を受けたビラの作成責任を担っていたのは解放派シンパであった。社青同中央(革労協としては採択について激しい論争が起き意見がまとまらなかった)で「組織内部糾弾闘争〈内糾〉路線」を採択。これに乗じて、党内で力をつけていた狭間嘉明ら革労協学生委員会中心の武闘派グループが滝口弘人・高見圭司を中心とする労働者活動家グループと対立を強める。内糾本部は連日神奈川大学宮面寮にあった査問室に反対派の疑いがある活動家を呼び出し、スパイ、差別者、と攻撃し自己批判を迫った。これらの内糾本部の活動に対し潮流を問わず多くの活動家から批判の声が上がったが、その暴走を止められる者はいなかった。当初は反内糾の意思表示をしていたのに、その後内糾本部に与する活動家も多く現れた。
狭間派と労対派の分裂[編集]
- 1980年9月15日 かねてから党内闘争が継続されていたが、ついにこの日三里塚において狭間に与するグループが滝口に与するグループを武装襲撃。これによって、解放派・革労協の組織的分裂が決定的となる。この後も狭間派は後の解放派全協に結集する活動家に対して武装襲撃を繰り返し、拉致・監禁という事態も発生し、負傷者まで出した。
- 1981年6月頃までに永井、狭間、けん(いわゆる「NHK」)らの狭間派(学生の半分と労働者の一部)と、滝口、高見ら他称「労対派」(後の革命的労働者党建設をめざす解放派全国協議会、通称解放派全協)(学生の半分と労働者の多数)に分裂。分裂を機に解放派社青同は事実上機能を停止する。
- 分裂の過程において、狭間派にも労対派にも与しないでそのまま解放派から離脱するメンバーも多数出現した。元々、解放派が狭間派のような過激な武装闘争を主張する極左的集団から、労対指導部よりもさらに右で、社会主義協会、さらには社会党に近い主張をする社民サンディカリスト的な集団をも含んだ統一戦線であったために、中原書記長暗殺以後の軍事化路線への傾斜及び内部糾弾闘争の党内派閥の政治的引き回しに嫌気がさしてそのまま脱落したものが後を絶たなかったのである。
- 1981年 現代社を追われた滝口らの革労協総務委員会反主流派グループ(思想的には彼らが本流なのは皮肉だが)と狭間ら学生委員会の武闘派らのスターリズム的なやり方に異を唱えた活動家らは、81年に機関紙「プロレタリア革命(後に連帯に改題)」を発行し狭間らを「宗派グループ」と規定して対立を強めた。分裂直後に75年創造社襲撃メンバーや東水労組合員などの労働者活動家及び神奈川大学の学生活動家(通称:4.20グループ)らが狭間派らの襲撃を受け負傷者を出すが、労対派は狭間派のような「個人テロル」という手段を用いた反撃はしなかった(集会などでの小競り合いはあった)。滝口らのグループは正式な公然拠点を連帯社とし、革労協再建を全国の社青同メンバーらに訴えるが現在では革命的労働者党建設をめざす解放派全国協議会を名乗り、初期解放派の思想を体現した組織の建設を行っている。
- 1999年 滝口弘人死去。
この前に書かれた内容だが、短い眠りの連続の中で見る夢(妄想)が面白い、ということには大いに同感である。「老いていくと身軽になる」というのも同感。俗世の義理をどんどん捨てて、好きなことだけしていればいいし、周囲への責任もあまり要求されないのが老年だ。
(以下引用)
「1年380日の晩酌!」老いていく自分自身の体を面白がる
それに、老いていくと身軽になる。会社や仕事、種々雑多なスケジュールに冠婚葬祭の義理事も減り、書くのも締め切りにそう追われることもなく、毎日だいたい原稿用紙で8枚から10枚くらいを埋めていくばかり。両手をパソコンのキーボードに乗せて、いつものキーの位置にぴたりと指があたらなくなったのは、両手が縮んだのでしょう。ピアニストがピアノの鍵盤の、決まったところに手を置くようなもので、思い通りに指が文字を打てなくなるのはちょっと困りますが、まあ、なんとか工夫して、やっている。
できなくなった物事を悔やんだって仕方ない。今もできることを全てと思って、やりくりすればいいだけの話。体の変調など大同小異ですよ。 =つづく
(聞き手=長昭彦/日刊ゲンダイ)
1:タイラスでの闘争と逃走
2:サントネージュでの権力闘争
3:フロス・フェリの一味の話
4:副主人公の赤毛の青年の話
などになるかと思う。それに加えて、大魔導士やその一味の話もある。
- 1964年(昭和39年)
- 名神高速道路・首都高速道路、東海道新幹線開通。10月10日-10月24日、東京オリンピック開催。
- 1965年(昭和40年)
- 日韓基本条約調印。証券不況(構造不況)。
- 1966年(昭和41年)
- 日本の総人口が1億人を突破。いざなぎ景気。ビートルズ来日。三里塚闘争開始。
- 1967年(昭和42年)
- 初の建国記念日の適用。公害対策基本法公布。四日市ぜんそく裁判が提訴される。
- 1968年(昭和43年)
- 小笠原諸島が本土復帰。三億円事件。東大紛争や日大紛争などの全共闘運動が激化。漫画『ゴルゴ13』の連載開始。
- 1969年(昭和44年)
- テレビアニメ『サザエさん』の放映開始。東名高速道路全線開通。
- 1970年(昭和45年)
- 3月14日-9月13日に日本万国博覧会(大阪万博)開催。よど号ハイジャック事件。三島事件。
昭和後期(ポスト高度経済成長期からバブルまで)の年表[編集]
- 1971年(昭和46年)
- 7月1日に環境庁設置。ニクソン・ショック。カップヌードル発売。
- 1972年(昭和47年)
- 札幌オリンピック開催。あさま山荘事件。山陽新幹線の新大阪駅-岡山駅間が開通。テルアビブ空港乱射事件。千日デパート火災。沖縄返還。日本列島改造論。日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(日中共同声明、台湾断交)。
- 1973年(昭和48年)
- 中東戦争による第一次オイルショック。金大中事件。大洋デパート火災。
- 1974年(昭和49年)
- 連続企業爆破事件。田中金脈問題。セブン-イレブン日本第1号店開店。
- 1975年(昭和50年)
- 3月10日に山陽新幹線の岡山駅-博多駅間が開通。沖縄国際海洋博覧会開催。
- 1976年(昭和51年)
- ロッキード事件。王貞治がベーブ・ルースの本塁打記録を抜く。
- 1977年(昭和52年)
- 北朝鮮による日本人拉致問題が盛んになる。王貞治#756号本塁打:ハンク・アーロンの本塁打記録を抜き世界一となる。ダッカ日航機ハイジャック事件。
- 1978年(昭和53年)
- 日中平和友好条約調印。新東京国際空港(現・成田国際空港)開港。第一回隅田川花火大会。
- 1979年(昭和54年)
- イランイスラム革命による第二次オイルショック。テレビアニメ『ドラえもん』(第2期)の放送開始。東京サミット。インベーダーゲームが流行[102]。日本坂トンネル火災事故。元号法成立。
- 1980年(昭和55年)
- ハプニング解散。大平正芳が急死。原宿で竹の子族が出現[103]。新宿西口バス放火事件。
- 1981年(昭和56年)
- 中国残留孤児が初来日する。建築基準法の施行令改正(新しい耐震基準)。神戸ポートアイランド博覧会。
- 1982年(昭和57年)
- ホテルニュージャパン火災。東北新幹線(大宮駅-盛岡駅間)、上越新幹線(大宮駅-新潟駅間)開通。3月18日に川崎公害裁判が開始。
- 1983年(昭和58年)
- 東京ディズニーランド開園。日本海中部地震発生。おしんブーム。
- 1984年(昭和59年)
- グリコ・森永事件。高円宮家創設。
- 1985年(昭和60年)
- 東北新幹線と上越新幹線・大宮駅-上野駅間が開通。4月1日、日本電信電話公社・日本専売公社が民営化されて、日本電信電話(NTT)・日本たばこ産業(JT)が発足。つくば科学博開催。8月12日日本航空123便墜落事故。G5でプラザ合意(昭和60年の円高不況)。
- 1986年(昭和61年)
- 男女雇用機会均等法執行。東京サミット開催。日本社会党の土井たか子が議会政党としては日本初の女性党首に就任。三原山噴火。
- 1987年(昭和62年)
- バブル景気(平成景気)が本格化。国鉄分割民営化でJRグループが発足される。
- 1988年(昭和63年)
- 青函トンネル、瀬戸大橋が開業。リクルート事件が問題化。テレビアニメ『それいけ!アンパンマン』の放映開始。
- 1989年(昭和64年/平成元年)
- 女子高生コンクリート殺人事件(発覚は1989年 (平成元年)3月)。1月7日に昭和天皇が崩御し、皇太子明仁親王の第125代天皇即位に伴い、翌8日に平成と改元される。