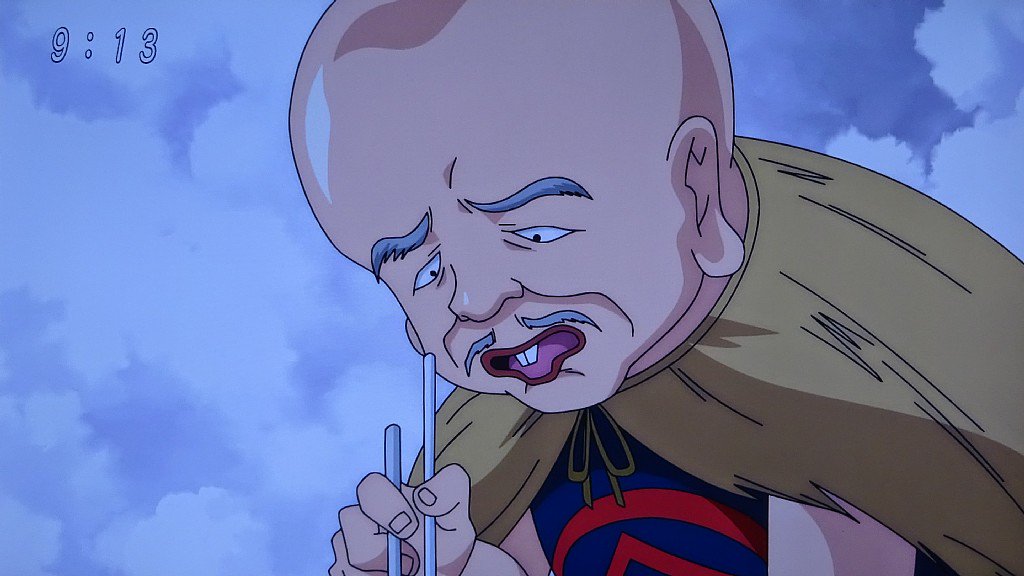それじゃオフビートな書き方や時代小説に外来語使うような文章は全部ダメじゃないかと。そういえば、井上ひさしの「直木賞のストライクゾーン」に関するエッセイで、あらかじめ決められた結末に向かうミステリは圏外と書いてあってゾッとしました。それらと無縁なライトノベルが爆発したのも当然ですよ
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
私も文章の拙劣な作家は苦手で、たとえば時代劇小説にカタカナ外来語が出るのも嫌いである。ただし、意図的なギャグとして用いるのと、文章への神経が粗雑なために時代劇に外来語を使うのは区別されるべきだろうと思うし、前者の場合でもユーモア感覚が低レベルなためにうんざりする場合がある。高橋三千綱の時代劇小説などがそんな感じだ。
基本的には、作家としての「誠実さ」や「真剣さ」の問題であり、大衆小説だからいい加減な書き方でいい、という作家の作品は一時は受けても長続きはしない。久生十蘭など、無数のジャンルの作品を書いたが、真剣に書いてない作品はほとんど無いと思う。だから長い作品生命がある。
なお、「あらかじめ決められた結末に向かう」作品、つまり登場人物が単に作家の操る人形でしかない作品は私も嫌いで、ミステリなどもほとんどは嫌いである。私が「シャーロックホームズ」が好きなのは、あれはミステリではなく冒険小説で、キャラが絶妙に優れているからだ。
また、私は松本清張は昭和を代表する文豪だと思っているが、彼の推理小説がやはり「あらかじめ決められた結末に向かう」作品でしかなく、数作しか読んでいないがまったく面白いとは思わない。しかし、彼の時代劇小説(特に長編)は、最高のエンタテイメントである。
つまり、小説で大事なのは読者を先へ先へを引っ張る「小説エンジン」だと私は思っているが、謎というのはその小説エンジンのひとつではあるがキャラクターが生きているかどうかほどの重要性は無い、と思う。たとえばジェイン・オースティンの「高慢と偏見」は、主人公の結婚問題がどうなるかという謎しか謎は無いが、それでも読者を先へ先へと引っ張る力は古今無双なのである。それは作中の人物たちが現実の人物よりはるかに面白く、現実の人物よりもはるかに生きているからだ。
-
-
昔の時代小説には平気でカタカナ外来語が使われていた話、存外みなさんに喜んでもらえたんだけど、実はこういう書き方は今は否定されてんですね。前にある人から「直木賞を狙うなら(僕には何の関係もないが)まず文章です。原稿用紙何枚かの間に一つでも同じ形容詞があったらダメとされます」と聞いて
図にするとわかりやすいな
分解したものを下ろすのがわからん
地下鉄のシールドマシンと同じ
一眼レフとは、カメラの構造の一種である。
ファインダーから見た光景をほぼそのままの状態で写真に撮影することができるのが最大の特徴。
概要
一眼レフカメラとは、光学ファインダーを備え、1つのレンズで撮影と構図決めの両方が可能なカメラの総称である。
一眼とはレンズが一つしか無いという意味。レフとはレフレックスの略で、カメラの内部にミラーを用い、像を反射させることでファインダーに像を送っていることを意味する。レンズを通した光景は普段はミラーを経由してファインダーへ送られているが、シャッターボタンを押した瞬間だけミラーが上がる事でフィルムまたは撮像素子に感光する。
旧来の銀塩フィルムを使用したタイプとデジタル一眼レフカメラに大別される。
しかし現在では銀塩フィルムタイプで生産が続けられている機種は極一部のみであり、大半はデジタル一眼レフであり、銀塩カメラは最早趣味の世界となっている。
一般的に一眼レフカメラと言うとレンズ交換式の印象が強く、実際にもそうした製品が大多数を占めるが、飽く迄も本体構造による分類なのでレンズ交換の可否は一眼レフの定義に関係無い。
ニコン最初期のズームレンズを搭載したニコレックス35ズームや興和のコーワフレックス、オリンパスがレンズ交換式から撤退後に出したLシリーズなど、少数ながらレンズ固定式の一眼レフカメラも存在した。オリンパスLシリーズのコンセプトには追随した会社もあり、コンパクトカメラとレンズ交換式一眼レフの橋渡しと言う意味でブリッジカメラと呼ばれた。